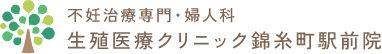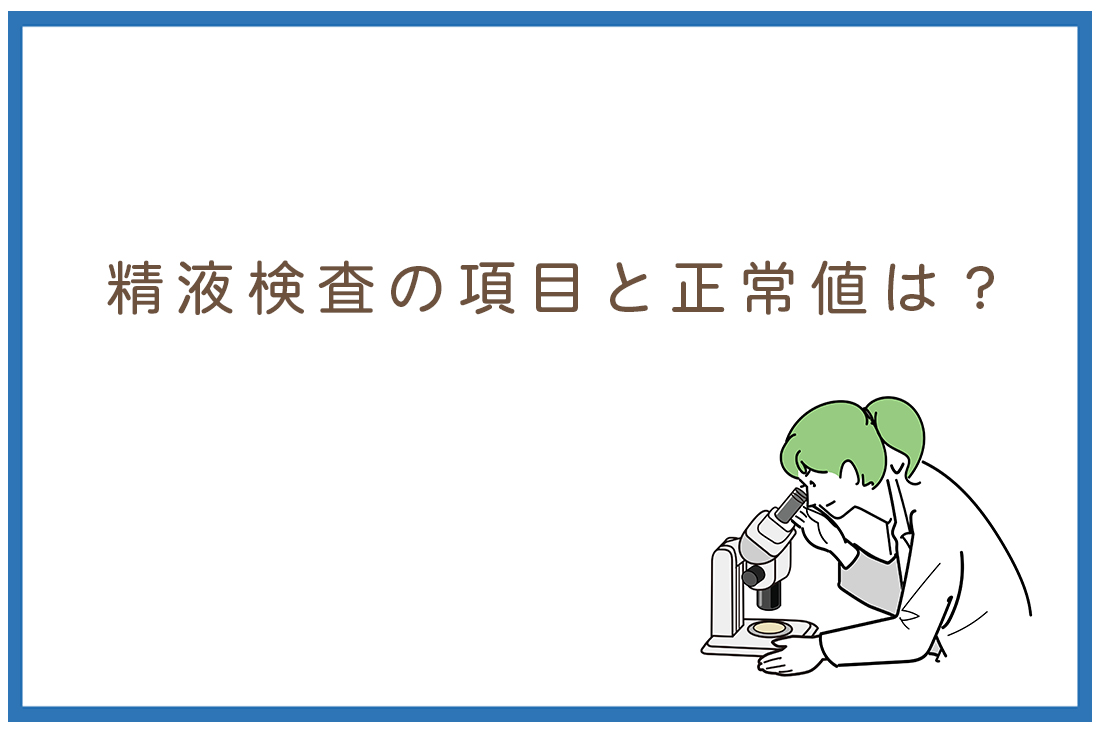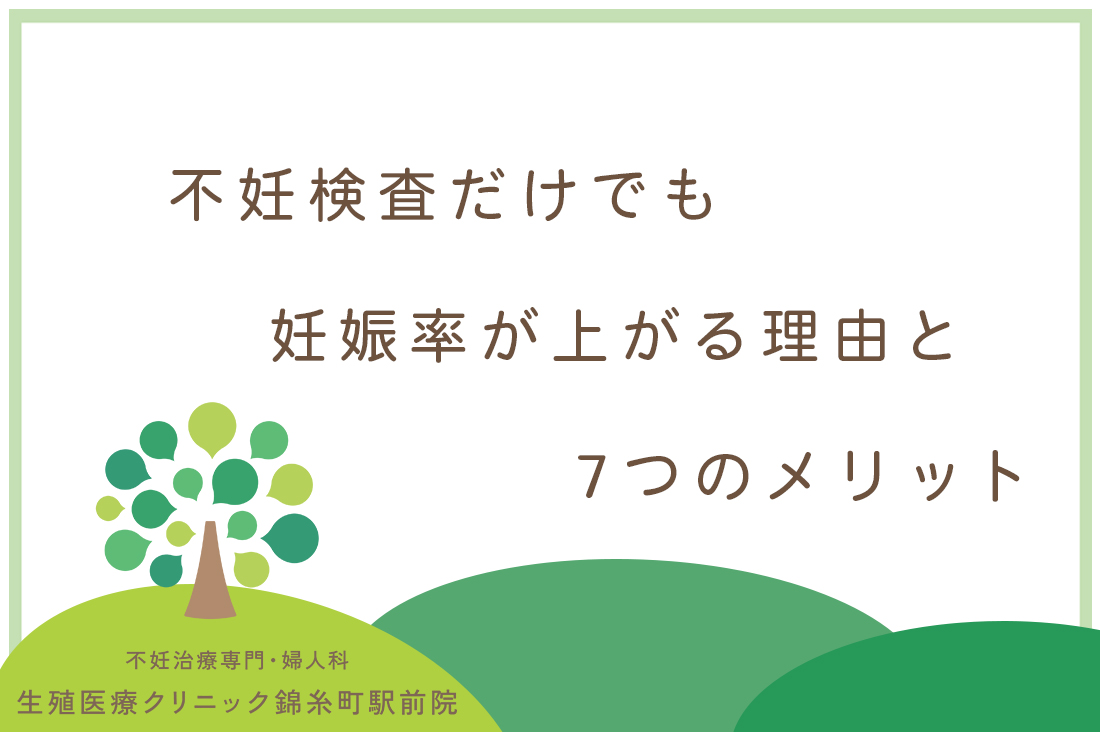「パートナーに精液検査を受けてもらいたいけど、どんな項目を調べるのか不安…」
「検査結果の数値の意味がよくわからない‥‥」
そんな悩みを抱えているご夫婦も多いのではないでしょうか?
不妊治療を始める際、女性側の検査に注目が集まりがちですが、実は不妊原因の約半数は男性側にあるとされています。私は胚培養士として長年多くの患者様の精液検査を行っていますが、少しでも早い段階で検査を受けられることこそが治療を進める上では非常に重要なのだと実感しています。
今回は精液検査で調べる項目について専門用語をわかりやすく解説しながら、最新のWHO基準や実際の不妊治療での活用方法まで詳しくお伝えしていきたいと思います。パートナーと一緒に読んでいただければ、検査への不安も軽くなるのではないでしょうか?
精液検査とは?不妊治療における重要性
精液検査が必要な理由
精液検査は男性の生殖能力を評価する最も基本的で重要な検査です。不妊症カップル全体の約48%で男性側の因子(男性側のみ、あるいは男性・女性両方)が関与しているデータが示されており、女性だけでなく男性も早期に検査を受けることが大切です。
精液検査では精子の数や運動性および形態など複数の項目を総合的に評価します。これらの結果から自然妊娠の可能性や人工授精、体外受精・顕微授精などの治療方法および媒精方法の選択が可能になります。
また精液検査は比較的簡単であり採血や造影検査のような痛みも無く身体への負担も少ない検査です。それでいて得られる情報は非常に多く治療方針を決める上で欠かせない検査といえます。
検査のタイミングと準備
精液検査を受ける際は検査の前に2~7日間の禁欲期間を設けることが推奨されています。禁欲期間が短すぎると精液量や精子濃度が低くなり、長すぎると運動率が低下する可能性があります。
精巣内で精子が造られる機能のことを造精機能といいますが、精子は体温より2~3度低い温度で造られるため高温の環境は造精機能に影響を与える可能性があります。検査前1週間は高熱環境(38度以上)のサウナや長時間の入浴は避けましょう。また生活習慣による影響も受けるため過度の飲酒や喫煙も控えめにすることをおすすめします。
検査当日はクリニックの採精室で採取する方法と自宅で採取してから持参する方法があります。自宅採取の場合は採取からおおよそ1時間以内に提出し人肌程度の温度(20~37度)で保温して運ぶことが大切です。冬場は特に温度管理に注意が必要です。
精液検査の基本項目を詳しく解説
精液量
精液量は1回の射精で出る精液の総量を測定します。WHO基準では1.4ml以上が正常とされています。精液量が少ない場合は「精液減少症」と呼ばれ、原因としては逆流性射精や精嚢の機能不全などが考えられます。
精液は液体部分である精漿と細胞部分である精子から構成されており、細胞の精子自体が占める割合はごくわずかです。精液は女性の生殖器内で精子が活動するための役割を果たしており、精液量が少ないと精子が子宮頸管を通過する際に不利になる可能性があります。
精液量は個人差が大きく同じ患者様であっても日によって変動することがあります。またその日の体調などによっても精液量が変動することもあります。1回の検査で精液量が少なくても過度に心配する必要はありません。
精子濃度
精子濃度は精液1mlあたりに含まれる精子の数を表します。WHO基準では1,600万/ml以上が正常とされています。精子濃度と精液量を掛け合わせた「総精子数」も重要な指標であり3,900万以上が正常値です。
精子濃度が低い状態を「乏精子症;oligospermia」と呼び、治療方針や媒精方法の決定に重要な情報となります。
実際の検査ではマクラ―チャンバーと呼ばれる専用の細胞計算版を使用して顕微鏡下で精子数をカウントしますが、最近では自動解析装置(SMASやSQAなど)を使用するクリニックも増えてきています。しかしながらやはり胚培養士が自身の”目”で確認できる能力を持っていることが重要だと思います。
運動率
運動率は、全精子に対する運動している精子の割合を示します。WHO基準では、全体の運動率が42%以上、前進運動精子率が30%以上を正常値としています。運動率が低い状態を「精子無力症;asthenospermia」と呼びます。
精子の運動性は下記の3つに分類されます。
| ⑴前進運動精子 | PR:Progressive motility (直線的または大きな円を描いて前進する精子) |
| ⑵非前進運動精子 | NP:Non-progressive motility (その場で動いているだけで前進しない精子) |
| ⑶不動精子 | IM:Immotile (全く動かない精子) |
前進運動精子は、卵管を通って卵子まで到達する能力を持つ精子として最も重要視され、人工授精や体外受精を行う上では、前進運動精子の割合が重要になります。
正常形態率(奇形率)
正常形態率(奇形率)は形態的に良好な精子の割合を示します。WHO基準では正常形態率4%以上(奇形率96%未満)が正常とされています。この数字は言い換えれば全体の95%の精子に何らかの形態異常があっても正常範囲内ということになり、この数値に驚かれる方も多いです。基準値よりも奇形の精子が多く認められる病態を「奇形精子症;teratozoospermia」と呼びます。
精子の形態評価では頭部と中片部および尾部それぞれを詳細に観察します。頭部の大きさや形と中片部の太さおよび尾部の長さや屈曲などをチェックします。形態的に異常があると精子の運動能力や受精能力に影響を与える可能性があると考えられており、加えて精子の遺伝子(DNA)にも何らかの異常がある可能性が考えられています。
最近では先進医療という枠組みにおいて高倍率下で精子を観察するIMSI(Intracytoplasmic Morphologically Selected Sperm Injection)という技術も導入されており、より詳細な形態評価が可能になっています。
WHO基準値(2021年最新版)と結果の見方
各項目の基準値一覧
2010年版から2021年に改訂された最新のWHO基準値(第6版)は以下の通りです。
| 精液量 | 1.4ml以上 (1.5ml以上) |
| 精子濃度 | 1,600万/ml以上 (1,500万/ml以上) |
| 総精子数 | 3,900万以上 |
| 運動率 | 42%以上 (40%以上) |
| 前進運動率 | 30%以上 (32%以上) |
| 生存率 | 54%以上 (58%以上) |
| 正常形態率 | 4%以上 |
※()内は2010年版基準値
これらの数値は、パートナーが12ヶ月以内に妊娠した男性の精液検査結果から算出された「5パーセンタイル値」です。つまり、妊娠に至った男性の95%がこの数値以上だったということを意味します。
第5版(2010年)と比較すると、精子濃度の基準値が1,500万から1,600万/mlに、運動率が40%から42%に引き上げられました。これは、より多くのデータが集積されたことによる改訂です。
基準値を下回った場合の考え方
基準値を下回ったからといって必ずしも妊娠ができないわけではありません。これらの数値はあくまでも統計的な指標であることや、また先述した通り精液所見はストレスや生活習慣および体調や環境などによって大きく変化するため、精液検査を行う度に変動することが多くあります。
重要なのは1回だけの検査で判断するのではなく複数の項目を複数回の検査によって総合的に評価することであり、WHOでも一定の間隔をあけて複数回の検査をもって総合的に判断を行うことが推奨されています。
例えば精液検査の結果として精子濃度が基準値をわずかに下回っている程度であれば、精液量が多ければ総精子数は基準値よりも多くなることもありますし、運動率や正常形態率などの他の項目が良好であれば十分に妊娠の可能性があります。逆にすべての項目をクリアしていてもすべて基準値ギリギリという場合には妊娠が難しくなる可能性があります。
精液検査のその他の項目
白血球数とその意味
精液中の白血球数は100万/ml未満が正常とされています。白血球が増加している状態を「膿精液症;leukocytospermia」と呼び、生殖器の炎症や感染症の可能性を示唆します。
膿精子症では白血球から活性酸素が放出され精子のDNAや細胞膜を傷つける可能性があり、これによって精子の運動率低下や受精能力の低下を引き起こすことがあります。また培養室で治療のために精液を処理する際に白血球が多い検体では良好な精子の回収率が顕著に低下することもよくあります。
精液中に白血球が継続的に認められる場合には細菌培養などの検査を追加で行い、原因となる感染症の特定と治療を行います。抗生物質による治療で改善することが多く治療後は精液所見の改善も期待できます。一方で慢性前立腺炎などが原因の場合は長期的な治療が必要になることもあります。
DNA断片化検査(DFI)
精子DNA断片化検査(DFI: DNA Fragmentation Index)は精子の遺伝情報であるDNAの損傷度を評価する検査です。通常の精液検査では評価できないより深いレベルでの精子の質を調べることができます。
DFIが高い場合は受精率の低下や胚発育の停止および流産率の上昇などと関連があることが報告されています。原因としては酸化ストレスや加齢および喫煙や精索静脈瘤などが挙げられます。最近の研究ではDFIが体外受精の成績に与える影響についても注目されています。
当院でも原因不明の受精障害や反復流産の方に対してDFI検査をお勧めすることがあります。DFIが高い場合は抗酸化作用のあるサプリメントの服用と同時に生活習慣を見直すことにより改善が期待できます。
胚培養士が見る精液検査のポイント
体外受精・顕微授精での活用
精液検査の結果は治療方針の決定や体外受精・顕微授精の媒精方法を決定する上で非常に重要です。私たち胚培養士は処理前の精液検査の結果と精子精製後の値を基に最適な媒精方法を患者様にご提案していきます。
精子精製によって良好な精子が多く回収できている場合では卵子に精子をふりかけるように受精させる体外受精(conventional IVF)が可能です。
一方で乏精子症や精子無力症の場合は精子精製後に良好な精子が回収できないこともよくあり、そのような場合には顕微授精(ICSI)を選択します。
精子精製では密度勾配遠心法やSwim-up法およびミグリスやZyMōtなどを用いた方法が一般的であり、これらのいずれかの方法によって運動性の良い精子を選別します。
処理後の精子の状態も重要であり、精子精製により濃度や運動率が大幅に改善することもあれば精子の性状によっては逆に低下してしまうこともあります。例えば精液中に白血球が数多く混在しているようなケースではもともとの精子の数や運動性に問題が無くても白血球が良好な精子の回収を著しく阻害してしまうことがあります。
私たちはこのような処理前の精液検査と精子精製後の状態を総合的に判断して媒精方法を患者様にご提案していきます。
検査結果の変動について
精液所見は同一人物でも検査ごとに大きく変動することがよくあります。実際に私自身の経験では精子濃度が±2~3倍で運動率が±20~30%の変動があった患者様も少なくありません。
変動の要因としては禁欲期間や採取時の心理的な状態および季節や環境と体調やストレスレベルなどがあります。また発熱を伴う感染症(近年よくあるケースでは新型コロナウイルス感染症やインフルエンザなど)に罹患した場合は約3ヶ月間精液所見に影響が出ることがあります。これは精子形成に約74日かかるためです。
このような変動があるため男性側に不妊の原因があるかどうかあるいは治療方針を決定するためには複数回の検査結果を参考にすることが大切です。また生活習慣の改善(禁煙、適度な運動、バランスの良い食事、ストレス管理)により精液所見が改善することも多くあります。例えば亜鉛やビタミンEおよびコエンザイムQ10などのサプリメントを継続的に服用することで改善がみられることもありますが、ただし大幅に/劇的にデータが改善するということはほとんどありません。
よくある質問と回答

Q1: 精液検査ではどのように精液を採取しますか?
A1: 用手法によって精液を専用のカップに採っていただきます。採精前は手を良く洗い、清潔な手で行うようにしてください。コンドームには、精子の動きを止める溶剤が付いていることもありますので、コンドームは使用しないでください。上手くカップに採れなかった場合や、こぼしてしまった場合は、必ず胚培養士やクリニックのスタッフにその旨をお知らせください。
Q2: 検査前日の飲酒は大丈夫ですか?
A2: 妊活・妊娠・不妊治療においては、基本的には男女ともアルコールは控えられた方がよいです。妊娠前後の飲酒は、少量であっても胎児に影響が出ることがあり、低体重、脳や神経の障害、発達遅延、先天性疾患(奇形)などの原因となる可能性があります。近年の研究で、カップルのうち男性にのみ飲酒習慣がある場合でも、胎児性アルコール症候群(FAS)や胎児性アルコール・スペクトラム障害(FASD)を引き起こすことが明らかになっており、妊娠の前から夫婦で一緒に飲酒を控えることが重要です。
もしも飲酒がやめられないという場合には、地域の保健センターや専門のクリニックを受診するようにしましょう。
Q3: 風邪薬を飲んでいますが、検査は受けられますか?
A3: 検査だけを受ける分には風邪薬の服用は問題ありませんが、風邪の症状によっては検査を延期した方がよい場合があります。特に、発熱の症状を呈している場合では、検査結果に影響が出ることがあるため延期することをお勧めします。また発熱症状がある場合、他の患者様へうつしてしまう可能性もあるため、クリニックへの来院を控えるようにしてください。
Q4: 仕事でストレスが多いのですが、影響はありますか?
A4: ストレスは精液所見に影響を与える可能性が指摘されていますが、ストレスの大きさや、感じ方はひとそれぞれですので、数値化することが出来ず、影響があると断言することはできません。
ただし、リラックスできる状態で検査を受けられた方が、外的な要因を受けづらくなり、より正確な値が出やすくなると思います。
お仕事のご都合もあると思いますので、まずは現状を把握することが大切です。
Q5: どのような時に再検査が必要ですか?
A5: 精液検査の主要4項目(精液量、精子濃度、運動率、奇形率)で異常所見が認められた場合に、再検査を受けられることをお勧めします。WHOでも、複数回の検査を以て総合的に判断することを推奨しています。