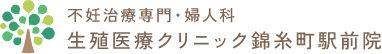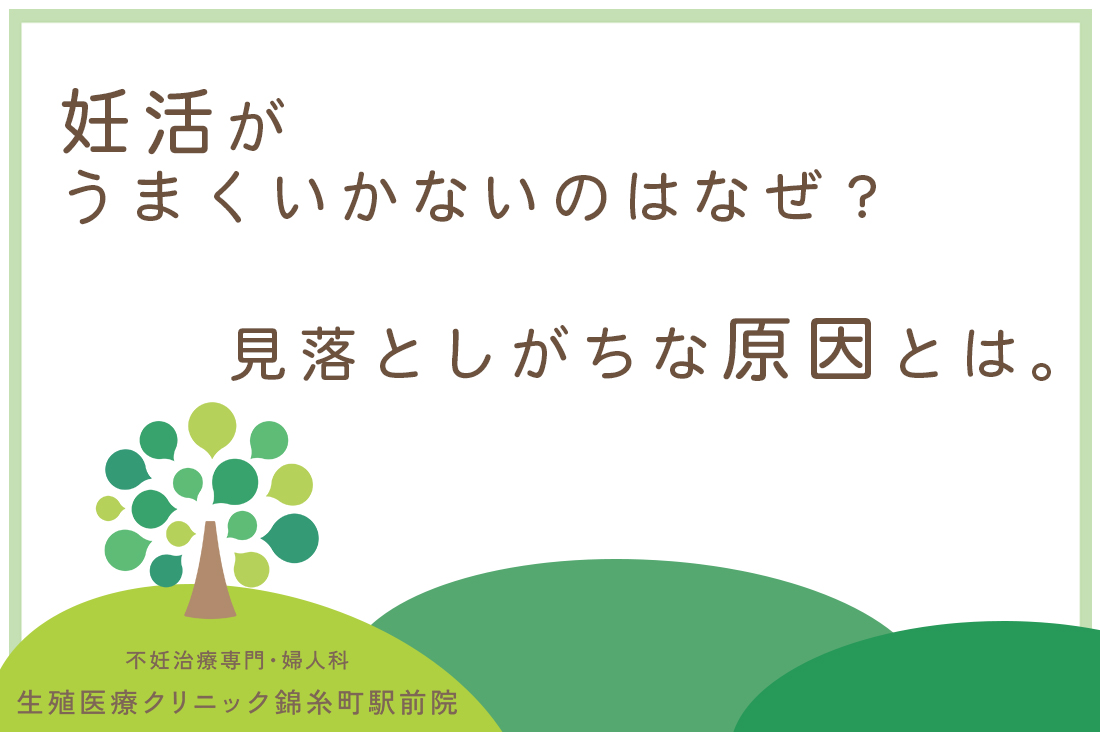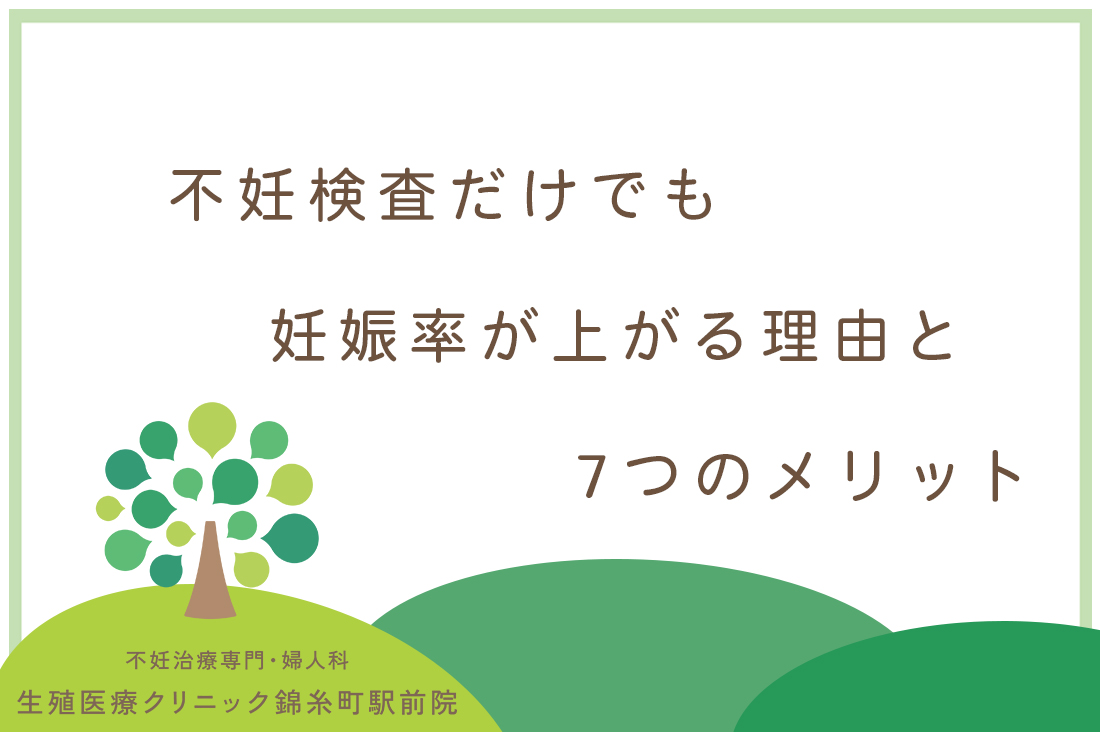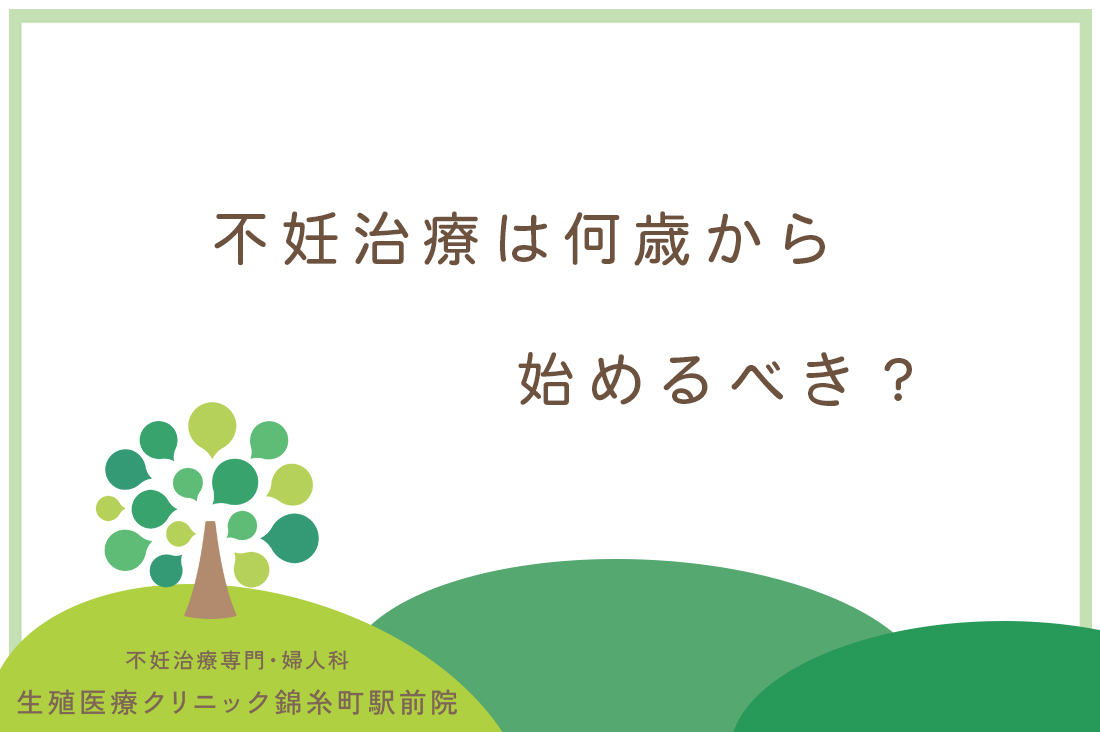「今月もリセット…」妊活を始めてから何度となく経験されていらっしゃる方も多いと思います。周りの友人の妊娠報告を心から喜べない自分に罪悪感を感じたりパートナーとの温度差に悩んだり。妊活がうまくいかないとき、心も体も疲れ果ててしまいますよね。
「私だけがうまくいかないのでは」と思われるかもしれませんが、実は多くの方が同じような悩みを抱えています。この記事では妊活がうまくいかない原因から具体的な対処法まで医学的根拠に基づいてわかりやすくお伝えします。一人で悩まず一緒に前を向いていきましょう。
妊活がうまくいかない主な原因
年齢による影響
女性の妊娠力は年齢とともに変化することは、多くの方がご存知かもしれません。しかし具体的にどのような変化が起きているのでしょうか。
35歳を過ぎると卵子の数が急激に減少し質も低下していきます。20代では約20%だった1周期あたりの妊娠率が35歳では約15%で40歳では約5%まで低下します。これは卵子の染色体異常等が増え卵子の質が低下することが主な原因です。
ただしこれはあくまで統計的な話。個人差は大きく40代でも自然妊娠される方もいらっしゃいます。年齢は確かに重要な要因ですが、それだけで諦める必要はありません。AMH(抗ミュラー管ホルモン)検査で卵巣予備能を調べることでより個別的な評価が可能です。
ホルモンバランスの乱れ
妊娠には複数のホルモンが絶妙なバランスで働く必要があります。特に重要なのがFSH(卵胞刺激ホルモン)とLH(黄体形成ホルモン)とエストロゲンとプロゲステロンです。
現代女性に多いのがストレスや不規則な生活によるホルモンバランスの乱れです。例えばプロラクチンというホルモンが過剰に分泌されると排卵が抑制されます。これは主に授乳期に上昇するホルモンですが、強いストレスでも上昇することがあります。
また黄体機能不全により高温期が短い(10日未満)場合、受精卵が着床しにくくなることがあります。基礎体温表をつけることでホルモンバランスの傾向が見えてきます。最近ではスマートフォンアプリと連動した基礎体温計も登場し記録が簡単になりました。必要に応じて基礎体温表などを活用して気になる症状があれば早めに相談することをおすすめします。
生活習慣の影響
妊活において生活習慣の改善は基本中の基本ですが、意外と見落とされがちな点があります。
まず喫煙は卵子の質を著しく低下させ閉経を平均2年早めるというデータがあります。受動喫煙でも影響があるため、パートナーの協力も不可欠です。アルコールについては適量(週2-3回、1回につきグラス1杯程度)であれば問題ないとされていますが、過度の飲酒は月経不順の原因となります。
体重も重要な要因です。BMI18.5未満の痩せすぎやBMI25以上の肥満、どちらも妊娠率を下げます。特に急激なダイエットは排卵を止めてしまうことがあります。理想的なBMIは20-24の範囲です。
睡眠不足も見逃せません。メラトニンというホルモンは抗酸化作用があり卵子の質を保護する働きがありますが、睡眠と密接に関わっていることが知られています。理想は22時~2時のゴールデンタイムに深い睡眠をとることですが、難しい場合でも7時間以上の睡眠時間は確保したいところです。
見落としがちな不妊の要因
男性側の要因
不妊の原因の約半数は男性側にあるにも関わらず、なぜか女性だけが検査や治療を受けているケースも多く見受けられます。
男性不妊の主な原因は精子の数が少ない(乏精子症)場合や運動率が低い(精子無力症)場合や奇形率が高い(奇形精子症)場合などです。これらは精液検査で簡単に調べることができます。WHO基準では精子濃度1500万/ml以上で運動率40%以上で正常形態率4%以上が正常とされています。
最近の研究では男性の精子の質も35歳を境に低下することがわかってきました。また精索静脈瘤があると精子所見に影響することもわかってきました。精索静脈瘤は男性不妊の約40%に見られ手術で改善可能です。
さらに生活習慣の改善も重要です。サウナや長風呂など精巣を温めすぎることやきついズボンや長時間の自転車走行は避けましょう。亜鉛やビタミンEやコエンザイムQ10などのサプリメントも精子の質改善に有効とされています。
子宮内膜症・多嚢胞性卵巣症候群
子宮内膜症は月経のある女性の約10%に見られる病気です。月経痛がひどい場合や性交痛がある場合や排便痛があるなどの症状があれば要注意です。
子宮内膜症があると卵管周囲の癒着により卵子のピックアップ障害が起きたり腹腔内の炎症により受精や着床が妨げられたりします。軽症でも妊娠率が低下することがわかっています。腹腔鏡手術で病巣を除去することで妊娠率が向上しますが、卵巣予備能が低下するリスクもあるため、治療方針は慎重に決める必要があります。
多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)は若い女性の5-10%に見られ排卵障害の最も多い原因です。月経不順やにきびや多毛などの症状があります。インスリン抵抗性が関与していることが多くメトホルミンという糖尿病薬が有効な場合があります。またBMIの高い方は体重減少だけで排卵が回復することもあるため、生活習慣の改善から始めることも大切です。
甲状腺機能の異常
甲状腺ホルモンは妊娠・出産に重要な役割を果たしていますが、症状が出にくいため見過ごされがちです。
甲状腺機能低下症(橋本病など)では流産率が上昇し排卵障害も起きやすくなります。疲れやすいことや冷え性や便秘や体重増加などの症状があれば要注意です。TSH(甲状腺刺激ホルモン)が2.5μIU/ml以上の場合、妊活中は治療を検討することが一般的です。
一方甲状腺機能亢進症(バセドウ病など)では月経不順や無排卵になることがあります。動悸や手の震えや体重減少や暑がりなどの症状が特徴です。
どちらも血液検査で簡単にスクリーニング検査ができ、専門医による適切な診断と治療により妊娠率は正常化します。妊活を始める前に一度は甲状腺機能をチェックすることをお勧めします。特に家族に甲状腺疾患の方がいる場合は要注意です。最近では潜在性甲状腺機能低下症という軽度の異常でも不妊や流産のリスクが上がることが知られています。
妊活がうまくいかないときのメンタルケア

ストレスと妊娠の関係
「ストレスは妊娠の大敵」とよく言われますが、これには科学的根拠があります。慢性的なストレスは視床下部-下垂体-卵巣軸というホルモン分泌システムを乱し排卵障害を引き起こします。
ストレスホルモンであるコルチゾールが上昇すると卵胞の発育が抑制され着床率も低下します。またストレスは免疫システムにも影響し受精卵を異物として攻撃してしまうこともあります。実際不妊治療中のカップルの約30%がうつ症状を経験するという報告もあります。
しかし「ストレスを感じないように」と言われても、それ自体がストレスになってしまいますよね。大切なのはストレスをゼロにすることではなく上手に付き合う方法を見つけることです。ヨガや瞑想やアロマテラピーなど自分に合ったリラックス法を見つけましょう。最近の研究ではマインドフルネス瞑想を行った女性の妊娠率が有意に上昇したという報告もあります。
パートナーとのコミュニケーション
妊活中は夫婦の温度差が問題になることが多くあります。女性は毎月の結果に一喜一憂し男性は「自然に任せればいい」と考えがちで、この違いが衝突を生むことがあります。
まず大切なのはお互いの気持ちを素直に伝え合うことです。「排卵日だから」という義務的な性交渉はかえって男性にプレッシャーを与えEDの原因にもなります。妊活は二人で取り組むものですので、情報を共有し一緒に病院に行き治療方針を二人で決めることが大切です。
定期的に「妊活会議」を開くのもお勧めです。月に1回お互いの思いや今後の方針について話し合う時間を作りましょう。その際責め合うのではなく「私は〇〇と感じている」というメッセージで伝えることがポイントです。
また妊活以外の会話や楽しみも大切にしましょう。デートや旅行など二人の時間を楽しむことで自然と絆が深まります。
専門家によるカウンセリング
一人であるいは夫婦だけで悩みを抱え込む必要はありません。不妊カウンセラーや生殖心理カウンセラーという専門家がいます。
カウンセリングでは治療への不安や周囲からのプレッシャーや夫婦関係の悩みなど何でも相談できます。「カウンセリングを受けるほどではない」と思われるかもしれませんが、早めに相談することで心の負担を軽減できます。
多くの不妊治療施設にはカウンセラーが常駐しています。またオンラインカウンセリングも増えており自宅から気軽に相談できるようになりました。ピアサポートグループへの参加も有効です。同じ悩みを持つ仲間と出会うことで「自分だけじゃない」という安心感が得られます。
最近では認知行動療法を取り入れたプログラムも開発されており、ネガティブな思考パターンを変えることでストレスを軽減し妊娠率の向上につながることが報告されています。
今すぐできる妊活改善法
基礎体温の正しい測り方
基礎体温は意外と正しく測れていない方も多いです。
まず毎朝同じ時間に起き上がる前に測ることが大切です。トイレに行った後では正確な値が出ません。舌下で5分間測るのが理想ですが、最近の電子体温計なら予測式で90秒程度で測定可能です。ただし予測式は実測式より誤差が出やすいのでできれば実測式をお勧めします。
睡眠時間が4時間未満の日や前日にアルコールを飲んだ日や体調不良の日は備考欄にメモしておきましょう。これらは基礎体温に影響します。
理想的な基礎体温は低温期と高温期の差が0.3℃以上で高温期が12-14日間続くパターンです。体温が低温期と高温期の2相性にならない場合は測定方法を見直すかホルモンバランスの乱れを疑います。
最近はウェアラブルデバイスも登場し自動で正確な基礎体温を記録できるようになりました。アプリと連動して排卵日予測もしてくれるので活用してみるのもいいでしょう。
栄養バランスの整え方
妊活に必要な栄養素は葉酸だけではありません。バランスの良い食事は卵子と精子の質を高めます。
葉酸は1日400μgを妊娠前から摂取することで神経管閉鎖障害のリスクを下げます。緑黄色野菜やレバーや納豆に多く含まれますが、食事だけでは不足しがちなのでサプリメントの併用をお勧めします。
鉄分も重要です。フェリチン(貯蔵鉄)が30ng/ml未満だと卵子の質が低下します。レバーや赤身肉やあさりや小松菜などを積極的に摂りましょう。またビタミンCと一緒に摂ると吸収率が上がることが知られています。
ビタミンDも見逃せません。血中濃度が30ng/ml未満だと体外受精の成功率が低下するという報告があります。日光浴(1日15分程度)やきのこ類や魚類から摂取できますが、日本人の約8割がビタミンD不足というデータもあるのでぜひ検査をお勧めします。
オメガ3脂肪酸(DHA・EPA)は炎症を抑え卵子の質を改善します。週2-3回は青魚を食べましょう。亜麻仁油やえごま油も良い供給源です。
適度な運動の取り入れ方
運動は妊活に良い影響を与えますが、やりすぎは逆効果です。
週3-4回で30分程度の有酸素運動が理想的です。ウォーキングやヨガや水泳などがお勧めです。激しい運動は活性酸素を増やし卵子の質を低下させる可能性があります。マラソンなどの持久系スポーツを頻繁に行う女性は月経不順になりやすいという報告もあります。
骨盤周りの血流を改善する運動も効果的です。骨盤底筋体操やヒップリフトやキャットポーズなどを取り入れてみましょう。骨盤周りの血流が改善すると子宮内膜が厚くなり着床しやすくなると考えられます。
ヨガは身体面だけでなく精神面にも良い影響があります。特に陰ヨガやリストラティブヨガは副交感神経を優位にしホルモンバランスを整えます。最近では「妊活ヨガ」クラスも増えており同じ悩みを持つ仲間と出会える場にもなっています。
運動を始める際は無理のない範囲から始め徐々に強度を上げていきましょう。体温が上がりすぎないようこまめな水分補給も忘れずに行いましょう。
医療機関を受診するタイミング
不妊治療を始める目安
「いつ病院に行けばいいの?」これは多くの方が悩む問題です。日本産科婦人科学会のガイドラインでは以下を受診の目安としています。
35歳未満の方は避妊をせずに1年間妊娠しない場合。35歳以上の方は6ヶ月が目安です。ただし月経不順がある場合や子宮内膜症の既往がある場合や性交痛があるなどの症状がある場合は年齢に関わらず早めの受診をお勧めします。
「まだ自然妊娠の可能性があるのでは」と思われるかもしれません。しかし検査をすることで原因が分かり適切な治療により妊娠への近道となることが多いです。例えば卵管が閉塞していればいくらタイミングを合わせても妊娠しません。
初診のタイミングは月経開始から3-5日目が理想的です。この時期にホルモン検査ができるためです。ただしこれを待って受診を遅らせる必要はありません。まずは相談だけでも構いません。パートナーと一緒に受診することでお互いの理解が深まりますので、可能であればお二人で受診していただくことをお勧めします。
初診で必要な検査
初診では問診の後、段階的に検査を進めていきます。すべてを一度に行う必要はありません。
女性側の基本検査にはホルモン検査(FSHやLHやE2やプロラクチンやAMHなど)と超音波検査(卵巣や子宮の状態確認)と子宮卵管造影検査(卵管の通過性確認)があります。これらの検査では不妊原因の約8割を占めています。
男性側は精液検査が基本です。3-5日の禁欲期間後に採取します。1回の検査では変動があるため、異常があれば2-3回検査をすることがあります。
その他クラミジア抗体検査や甲状腺機能検査や糖尿病検査なども行います。
検査費用は施設により異なりますが、多くの検査が3割負担で受けられるようになりました。
検査結果が出るまでに1-2周期かかることもありますが、その間も自然妊娠の可能性はあります。焦らず一つずつ進めていきましょう。
治療の選択肢
不妊治療には段階があり、原因や年齢や希望に応じて選択します。
まずタイミング療法から始めることが多いです。超音波で卵胞の大きさを測り排卵日を正確に予測します。排卵誘発剤を使うこともあります。3-6周期行い妊娠しなければ次のステップへ進みます。成功率は1周期あたり約5-10%です。
人工授精は精子を洗浄濃縮して子宮内に注入する方法です。精子の状態が良くない場合やタイミング療法で妊娠しない場合に行います。成功率は1回あたり約10%で、4-6回行って妊娠しなければ体外受精を検討します。
体外受精は卵子と精子を体外で受精させ受精卵を子宮に戻す方法です。卵管閉塞や重度の男性不妊や原因不明不妊などが適応です。採卵には麻酔を使うことが多く入院の必要はありません。成功率は年齢により大きく異なり、35歳未満で約40%で40歳で約20%で43歳で約10%です。
顕微授精は精子を直接卵子に注入する方法で重度の男性不妊に有効ですので、体外受精にて受精しない場合などに選択肢となります。
最新の不妊治療について
体外受精の成功率向上
体外受精の技術は日進月歩で進化しています。最新の技術により成功率が大幅に向上しています。
タイムラプスインキュベーターは培養器内で受精卵を連続撮影し細胞分裂の様子を観察できる装置です。これにより最も質の良い胚を選択でき妊娠率が約10%向上するという報告があります。培養器から取り出す必要がないため胚へのストレスも軽減されます。
培養液の改良も進んでいます。個々の胚に最適な培養条件を提供する「個別培養システム」により胚盤胞到達率が向上しています。さらにAIを活用した胚評価システムも開発され経験豊富な胚培養士と同等以上の精度で良好胚を選択できるようになってきました。
PGT-A検査の活用
PGT-A(着床前胚染色体異数性検査)は移植前に受精卵の染色体数を調べる検査です。
染色体数の異常がない胚を選んで移植することで流産率が大幅に低下します。通常の体外受精では流産率が約20-30%ですが、PGT-A後は約5-10%に減少します。また移植あたりの妊娠率も向上し結果として出産までの期間が短縮されます。
適応は反復流産(2回以上)や反復着床不全(良好胚を2回以上移植しても妊娠しない)や35歳以上などです。ただし検査により移植可能な胚が減ることもありすべての方に有効とは限りません。
検査費用は1個あたり10-15万円と高額で現在は自費診療です。また倫理的な配慮から性別判定はできません。検査を受けるかどうかは医師とよく相談して決めることが大切です。
最新の研究ではAIを使って胚の画像から染色体異常を予測する技術も開発されており、将来的にはより簡便で安価な検査が可能になるかもしれません。
卵子凍結という選択
社会的卵子凍結(医学的適応のない卵子凍結)が注目されています。将来の妊娠に備えて若いうちに卵子を凍結保存する方法です。
凍結技術の進歩により融解後の生存率は95%以上で受精率も新鮮卵子とほぼ同等になりました。ただし多くの施設では採卵や移植の際の年齢による制限を設けていますので、各施設の適応を確認していただくといいでしょう。
一般的には理想的な卵子凍結時期は35歳未満です。35歳で20個凍結した場合、1人出産できる確率は約75%という報告があります。ただし40歳での凍結では同じ20個でも確率は約35%に低下します。
費用は採卵・凍結で30-50万円で年間保管料が3-5万円で融解・移植で20-30万円程度です。自治体の助成金や企業の福利厚生として費用補助を行うところも増えています。
凍結卵子があることで心理的な安心感は得られますが、必ず妊娠できるわけではありません。また高齢出産のリスクは変わりません。パートナーができたらまず通常のプロセスでの妊娠を試みることをお勧めします。凍結卵子は「保険」として考え過度な期待は禁物です。