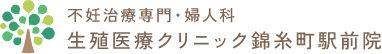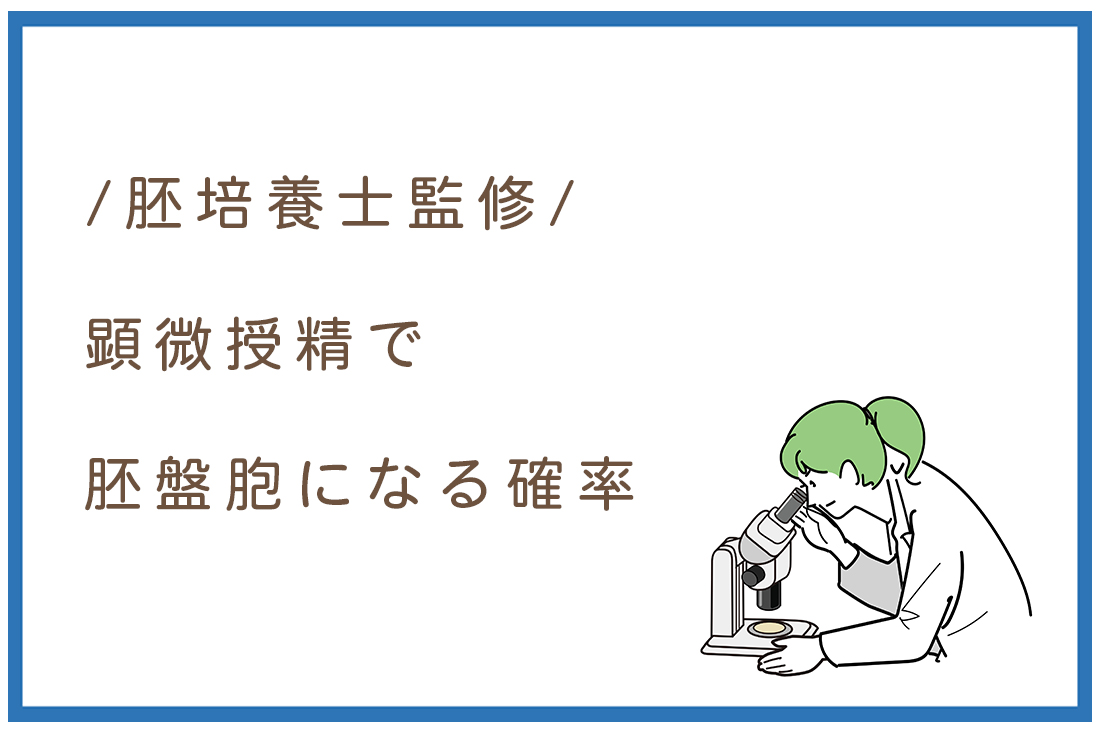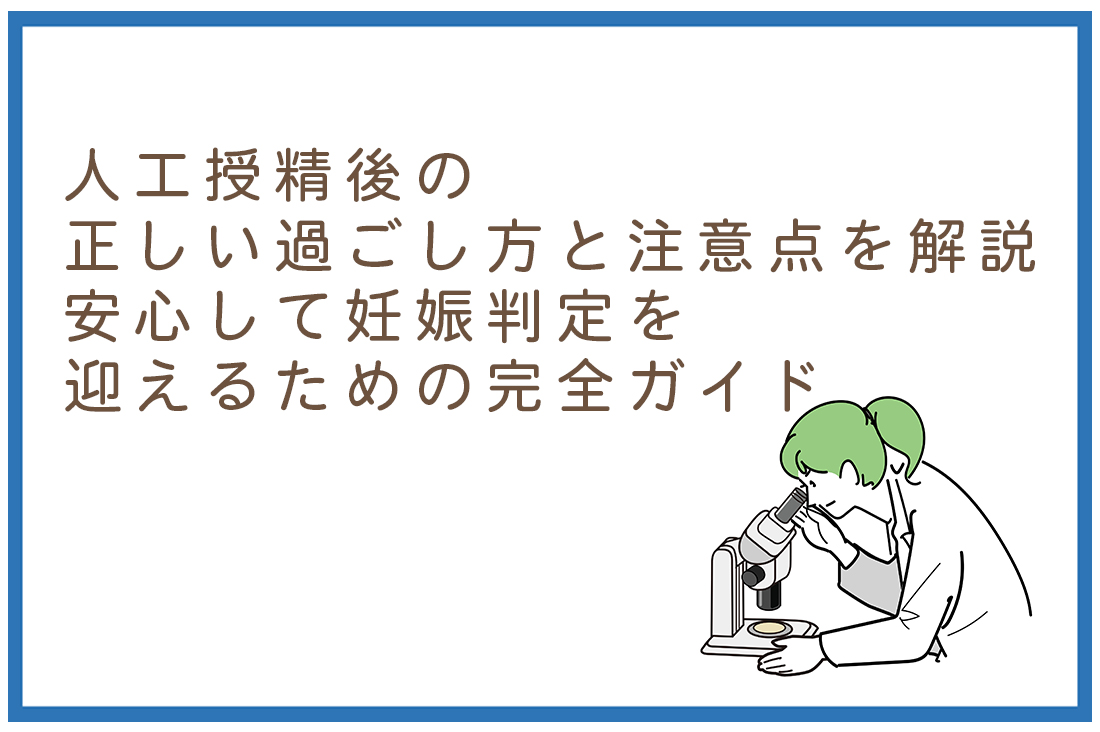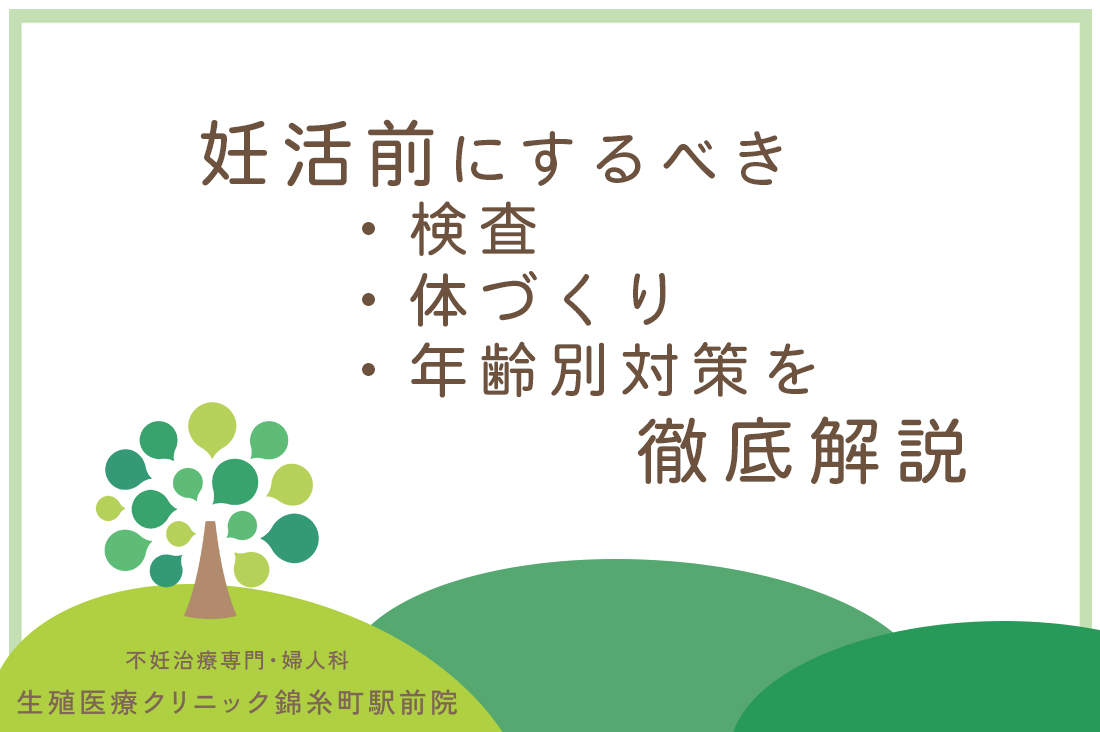目次
高度生殖医療によって成功に辿り着くためには、採卵で卵子が採れるか、媒精で無事に受精するか、受精卵が胚盤胞まで育つか、凍結や移植の基準を満たすか、移植した胚が着床するかなど数々のハードルを超えなければなりません。
特に「胚盤胞まで育つかどうか」は凍結や移植といった次の治療のステップまで進めるか否かがかかっているため、不安を抱く方は少なく無いようです。私自身胚培養士として15年以上多くのご夫婦を受け持ってきましたが、実際に「私の卵はいまどうなっていますか?」「無事に育っていますか?」と一週間の間に何度も何度もご連絡をいただく方もいらっしゃいます。
今回のコラムでは卵子が採れた後、培養室でどのように扱われているのかについて『成績改善に向けたポイント』なども分かりやすくお伝えしていきたいと思います。
顕微授精と体外受精の違いは?
顕微授精(ICSI)と体外受精(cIVF)は、いずれも卵子と精子を受精させる媒精(ばいせい)の手法です。ICSIとcIVFの2つの方法の大きな違いは、受精を成立させるためのプロセスと精子の卵子へのアプローチの方法にあります。
cIVFは卵子の周りに良好な運動精子を約10万個ふりかけて受精を図ります。クリニックによっては「ふりかけ法」と呼ぶこともあります。卵子と受精する精子は自然選択によって選ばれ、精子が自力で卵子の細胞に侵入します。
一方ICSIは胚培養士が顕微鏡下で1個の精子を選び、極細のガラス針を使って卵子の細胞内に直接穿刺して挿入します。そのため受精する精子は人の目によって選別が行われます。
卵子と精子が受精した後、受精卵(胚)が発育していく過程は体外受精でも顕微授精でも大きな違いはありません。
顕微授精における胚盤胞到達率の実際
よくいただく質問に、「顕微授精だと胚盤胞になりにくいといったことはありますか?」というものがあります。確かに、実際のデータではcIVFで受精したものの方がやや胚盤胞発生率が高い傾向にありますが、そこまで大きな差があるというわけではありません。
顕微授精の胚盤胞発生率が低く算出される理由とは
媒精方法を決定する際にICSIが選択されるケースとしては、
- 精子の数が少ない
- 精子の運動率が低い
- 形態的に奇形なものが目立つ
- 抗精子抗体が認められる
- 受精障害が認められる
- 卵子の細胞内に(ICSIが妥当とする)異常な所見が認められる
- 透明帯が極端に厚い
- 透明帯に異常が認められる
などがあり、ICSI由来胚の胚盤胞発生率のデータの中には、上記のような成績が下がってしまう可能性のあるバックグラウンドを持った症例が一定数含まれています。
そのため、上記のような症例を除いた場合では、cIVFでもICSIでも成績に大きな差は無いと考えられています。
年齢別の胚盤胞になる確率
胚盤胞発生率に最も大きな影響を与えるのが女性の採卵時の年齢です。
日本産科婦人科学会から報告されている最新版のデータ(2022年)と、当院での過去の成績における胚盤胞発生率は以下のようになります。
- ~30歳未満:受精卵の約50~70%が胚盤胞に発生
- 30~34歳:受精卵の約45~65%が胚盤胞に発生
- 35~39歳:受精卵の約35~55%が胚盤胞に発生
- 40~42歳:受精卵の約25~45%が胚盤胞に発生
- 43歳以上~:受精卵の約10~20%が胚盤胞に発生
あくまでもこれらは胚盤胞にまで到達する確率であり一定の基準を満たさなければ凍結・移植を行うことは出来ません。またこれらの数値はおおよその平均値でありこのデータよりも良い症例/悪い症例は存在します。
これらの数字を見てがっかりされた方もいらっしゃるかもしれませんが、われわれ医療従事者が妊活・妊娠における『年齢の重要性』を繰り返し厳しく説くのは、このような具体的なデータが存在するためです。
なぜ胚盤胞まで育つことが重要なのか
そもそもなぜ胚盤胞まで育てるのか?ということですが、胚盤胞に育てる主なメリットとして、
胚移植時の着床率が初期胚と比較して有意に高い
単一胚移植でも高い妊娠率が得られる(多胎妊娠のリスクを避けられる)
胚移植に向けて子宮内膜との同期(タイミング)を調整しやすい
などがあり、加えてこのようなメリット以外にも”生物学的な淘汰”という目的があります。
妊娠の可能性の無い胚や染色体異常のある胚の多くは受精や分割が見られても最終的に胚盤胞に成長する前に発育が停止してしまうことが多いです。分割期胚(初期胚)の段階で凍結あるいは移植をしてしまうと、そのまま培養を継続した場合に胚盤胞まで育っていなかった可能性があるため、このような胚を選別して赤ちゃんになる可能性の無い胚を淘汰していくという考え方です。
「淘汰」という言葉は冷たく聞こえるかもしれませんがこれは決してネガティブな意味ではなく、妊娠の可能性の高い胚をしっかりと見極めることで無駄な凍結や移植を減らし患者様のお身体だけでなく費用面での負担も軽減することができます。
受精卵が胚盤胞になるまでの過程
Day1:受精確認(前核の観察)
体外受精または顕微授精の翌日、最初に観察するのが「受精したか否かの確認」です。
正常受精の場合、卵子の細胞の中に2つの前核(雄性前核と雌性前核)と、細胞の外側に2つの極体が観察されます。
胚によっては、前核の大きさが不均等だったり位置が離れていたりすることもあり、その後の発生にどの程度影響するかも含めて慎重に観察していく必要があります。
前核が3個以上の場合は異常受精で、赤ちゃんになる可能性は無いためこの時点で培養を中止します。
Day2~3:細胞の分割の確認
受精確認の翌日から、受精卵は分割(細胞分裂)を始めていきます。Day2で4細胞期、Day3で8細胞期に成長していることが理想的な成長スピードです。ただし、分割のスピードには受精卵個々の「個体差」があります。同じ方から採れた卵子で、同じ媒精方法、同じ媒精時間であっても、成長のスピードは同一では無くそれぞれ異なります。
分割期胚では、Veeck分類と呼ばれる胚の評価方法(グレード)があり、
- 細胞のサイズの均等性:各細胞(割球)の大きさが揃っているか
- フラグメンテーションの量:細胞破片がどの程度あるか
を詳しく観察していきます。
Day4:Compaction期~桑実胚
Day4になると、分割が進んだ細胞同士が融合し始め(Compaction期胚)、その後は桑の実のような形に発生していきます。この状態を「桑実期胚(そうじつきはい)」と呼びます。
Day5~6:胚盤胞への到達
Day5~6になると、いよいよ胚盤胞へ向けて発育が進んでいきます。桑実期胚の中に小さな空洞(胞胚腔)ができ始め、そこから徐々に拡大していきます。Day5の段階で胚盤胞にならなくても、引き続き培養を継続して、Day6の朝あるいは夕方でやっと胚盤胞に成長してくることもあります。胚盤胞では、Gardner(ガードナー)分類と呼ばれる国際的な評価方法があり、胚の大きさや状態を表す数字(1~6)と、胚盤胞を構成する2つの箇所についてアルファベット(A~C)の組み合わせでグレードを付けていきます。
胚盤胞発生に影響を与える要因
卵子の“質”と年齢の関係
いわゆる「卵子の“質”」は「卵子の“老化”」と表現されることもありますが、より具体的に言うと、
- 卵子のミトコンドリアの機能:細胞のエネルギー産生に関わる
- 卵子の染色体の状態:年齢とともに染色体異常が増加
が挙げられます。
しかしながら、同じ年齢でも⑴・⑵が生じる影響には個人差は非常に大きく、生活習慣や体質、ストレスレベルなども大きく影響します。年齢の若い方でも、喫煙や飲酒といった習慣のある方や、過去に大きな病気をしたり、生殖細胞に影響のある薬剤の服薬例があったりする場合には、妊娠において「年齢が若い」という恩恵は受けにくくなってしまいます。
精子が与える影響
当然ながら胚は卵子と精子が融合した細胞であるため、精子側の要因も極めて重要です。顕微授精では「良好精子が1個あれば治療を進めることは可能」と言われますが、やはり精子の”質”も胚盤胞発生率に影響します。
特に重要なのはDNA断片化率(精子DNAの損傷の割合)や精子の成熟度や精液中の酸化ストレス(活性酸素による精子への影響)などで、近年の研究では男性の生活習慣の改善(禁煙、抗酸化物質の摂取、適度な運動など)によって胚盤胞発生率に向上が見られたとする研究も報告されています。
培養技術と培養環境の重要性
培養室の環境も胚の成長に直接影響します。特に注意が必要となるのが温度管理やpH管理やガス濃度や適切な培養液の選択やインキュベーターの扉の開閉を最小限にする操作や胚へのストレスの軽減や顕微授精の技術力や精子の選択眼(良好な形態と運動性の評価)や卵子へのダメージ最小化や適切な媒精や観察のタイミングなどです。当院では主に臨床経験5年以上の胚培養士が検体を取り扱うようにしています。
成績改善のためにできること
禁酒・禁煙
喫煙・飲酒は、卵子の“質”を低下させる代表格の習慣です。特に喫煙は、直接的な不妊症の原因となるほか、ご夫婦のいずれかあるいは両方に喫煙の習慣があった場合、妊娠率が半減するという具体的なデータも示されています。また、妊娠後の母体・胎児へのリスクも顕著に増加させます。
バランスの良い食事
栄養が不足している状態は、卵子や精子の質の低下や胚盤胞発生率の低下につながります。特にタンパク質、鉄・亜鉛などのミネラル、ビタミンB群、ビタミンC、葉酸などが不足すると、胚の発育を阻害してしまう可能性も指摘されています。栄養に偏りの無い、バランスの良い食事を心がけ、暴飲暴食も控えるようにしましょう。
十分な睡眠
質の良い睡眠は、卵子の“質”に直結します。これは、夜の寝ている時間帯に最もホルモンの分泌が調整されるためです。最低でも7時間はしっかりと睡眠を取ることが重要です。また、体内時計を整えるために、決まった時間に入眠し、決まった時間に起床することを習慣づけていくことも大切です。
適度な運動
適度な運動習慣を付けることは、妊活や不妊治療に良い働きをするだけでなく、
生活習慣病の予防や健康増進にも働きます。しかしながら、過度な運動は逆効果になってしまいますので注意が必要です。ランニングやサイクリングなどで「軽く汗をかく程度」が理想で、短い時間であっても継続して運動する習慣を付けていくということが重要です。
体重管理
ヒトの肥満度の判定に用いられる体格指数にBMI(Body Mass Index)があります。男性も女性も、BMI 18.5未満の痩せ型、BMI 25以上の肥満型は、不妊の直接的な要因となることが知られています。痩せ型や肥満型では、妊娠後に胎児・母体へのリスクが増加することも知られています。体重のコントロールは健康的な妊娠を迎えるためには必須であり、クリニックによっては、適正体重にならなければ治療を開始しないとするクリニックもあります。
サプリメントの摂取
食事で摂りづらい栄養素は、サプリメントで積極的に摂取していく必要があります。
女性では、不足しがちな栄養素として、
- 葉酸(一日推奨量640μg)
- 鉄
- ビタミンD
- DHA・EPA
があります。
男性では、不足しがちな栄養素として、
- 亜鉛
- ビタミンC
- ビタミンE
- コエンザイムQ10
などがあります。ただし、サプリメントは「魔法の薬」ではなく、あくまでも不足している栄養素を補うものです。基本的な食事と生活習慣の改善が大前提です。
ストレス管理の重要性
ストレス状態が不妊治療の結果に影響を与えるということは、医学的にも示唆されています。ストレスが高い状態では、コルチゾールというホルモンが増加し、卵子の質や胚の発育に悪影響を与える可能性が指摘されています。
効果的なストレス管理法としては、ヨガや瞑想、趣味の時間を持つことや、クリニックでのカウンセリングなどを通じて、不妊治療専門家と不安を共有するということもストレス管理に役立ちます。
卵巣刺激法の見直し
採卵に向けた卵巣刺激には、PPOS法、アンタゴニスト法、ロング法、ショート法、低刺激(クロミフェン)、完全自然周期など様々な方法があります。どの方法が適しているかは、患者様の病歴や体質などのバックグラウンドによっても変わることもあるため、一度の採卵で上手くいかなかった場合は、画一的な治療を繰り返すのではなく、卵巣刺激方法を見直すことで、成績が改善することもあります。
よくある質問(Q&A)

Q1: 顕微授精の方が体外受精より胚盤胞になりにくいと聞きましたが本当ですか?
A1: 数字上では体外受精の方が成績は高い傾向が見られますが、顕微授精を選択する場合、精子の数が少ない、運動性が悪い、卵子に特筆する所見がある、などの成績が低下する可能性のあるバックグラウンドを持った症例(顕微授精を選択せざるを得ない症例)が一定数含まれており、このような症例を除くと体外受精でも顕微授精でも成績に大きな差は無いと考えられています。
Q2: 採卵数が少ないと胚盤胞になる確率も下がるのでしょうか?
A2: 採卵数がどんなに多くても、卵子の“質”が低い場合では、胚盤胞発生率は低くなってしまいます。採卵数と、卵子のポテンシャルはまったく別で、たとえ卵子が1個でも、年齢が若く質の良い卵子で、同時に精子の状態も良好であれば、十分に胚盤胞に発育します。
Q3: Day5で胚盤胞にならなかった胚はあきらめるべきですか?
A3: Day6の朝や夕方に胚盤胞に発育してくることもあります。特に40歳以上の高齢の方では、ゆっくり成長する胚が多い傾向があるため、慎重に経過を追っていく必要があります。
Q4: グレードの低い胚盤胞でも妊娠の可能性はありますか?
A4: グレードはあくまでも形態的な(見た目だけの)評価であり、胚の“中身”を反映するものではありません。より具体的に言えば、胚の染色体の正倍数性は見た目では判断することが出来ず、着床・妊娠するかどうか、出産に至るかどうかが、胚の染色体が正常であることが必須です。グレードAAの胚盤胞で移植に失敗し、グレードCCの胚盤胞から健康な赤ちゃんが生まれることも実際にあります。
Q5: 夫の生活習慣も胚盤胞になるかどうかに影響しますか?
A5: 極めて大きく影響します。精子は、精子のもとになる細胞から、体外に射出される精子が形成されるまでに約74日かかると考えられているため、治療当日の2~3ヶ月前からの生活習慣改善(禁煙、禁酒、禁欲期間の管理、適度な運動、食生活、ストレス管理など)に気を付けていくことが重要です。実際に、一般的な精液検査に数値として表れない潜在的な男性不妊も数多く存在します。
まとめ – 前向きに治療に臨むために
今回のコラムでは顕微授精を実施した時に胚盤胞になる確率や成績の改善に向けたポイントについて解説を行ってきました。
治療を進めていく中で不安を感じるフェーズに度々直面するかもしれません。特に「胚盤胞まで育つかどうか」は次の治療ステップに進めるかどうかが決まる重要な局面であるため、誰しもが不安を感じるかと思います。
ですがもしも胚盤胞まで成長しなかったとしても、それは『ただの失敗』ではありません。その経験は次により良い結果をもたらすための貴重な情報となり得る可能性があります。私たち医療スタッフはその結果を次に生かすために日々技術を磨き知識を増やしています。
最後にこのコラムを読んでいる方の中には採卵を終えてから数日間毎日ドキドキしながら結果を待っているという患者様もいらっしゃるかと思います。
胚盤胞に無事に成長しても胚盤胞にならなくても、先述したように治療は前に進んでいると少しでもポジティブに捉えていただけるとストレスの軽減にもつながり将来的にもきっと良い結果が得られるのではないでしょうか。
当院は朝8時から夜21時まで、土日祝も診療しています。お仕事前やお仕事帰りに、まずは相談だけでもいらしてください。(錦糸町駅徒歩4分)