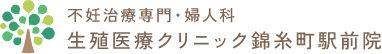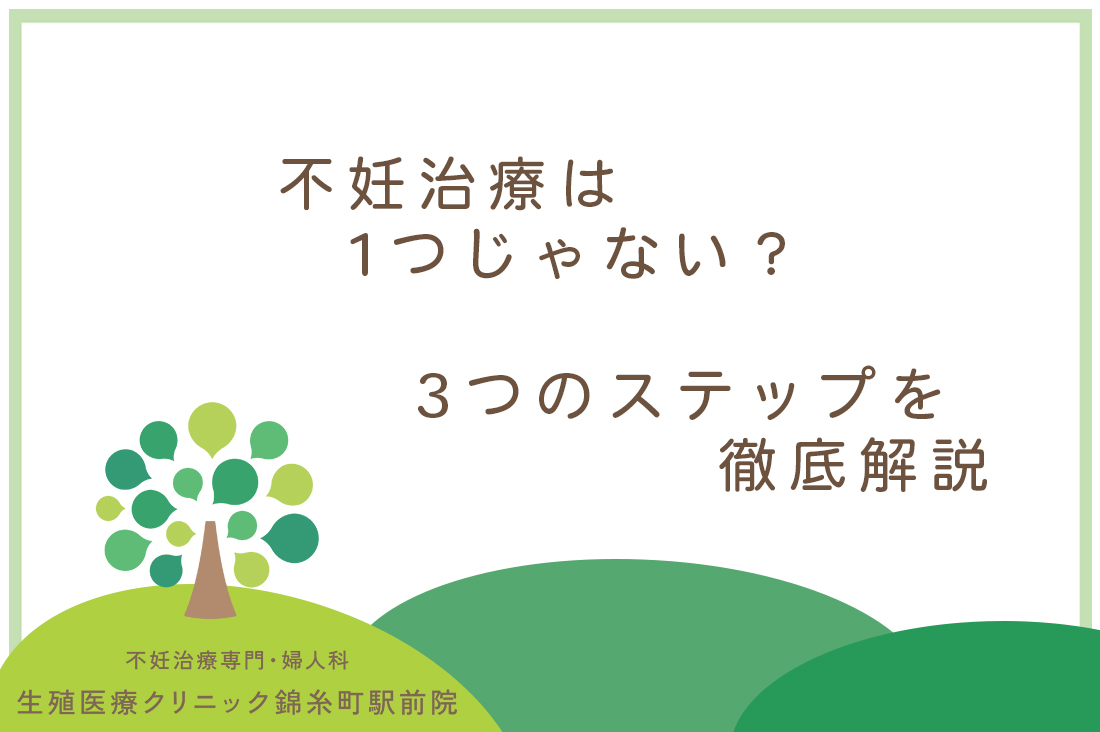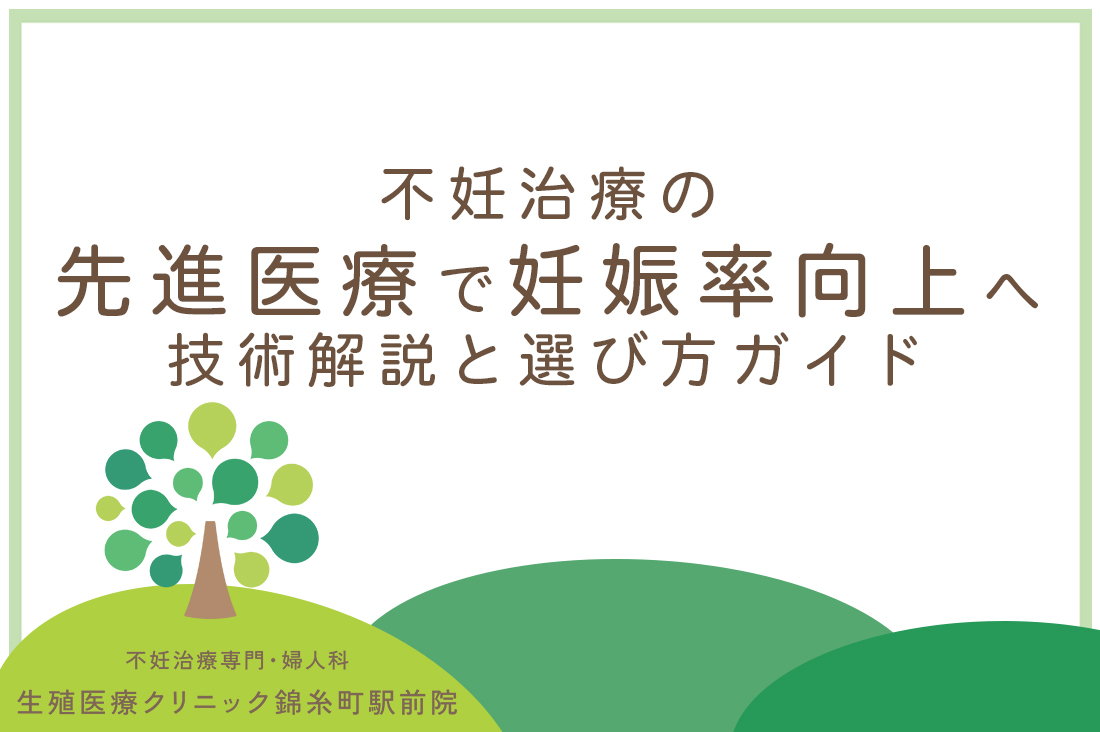目次
「赤ちゃんを授かりたい」その願いを胸に、不妊治療について調べ始めたあなた。でもタイミング法や人工授精や体外受精…専門用語が多くてどこから始めればいいのか不安になっていませんか?
専門医としてこれまで多くの治療に携わってきた経験からお伝えしたいことは「不妊治療にはいくつかの治療のステップがあり、これまでの経緯によって治療のアドバイスは行いますが、すべての方が同じステップを歩む必要はなく最終的な選択はアドバイス通りではなくお二人で決定していい」ということです。
この記事では不妊治療の基本的なステップを分かりやすく解説するとともに、最新の治療オプションやお二人に合った治療の選び方についてもお伝えします。一緒に治療への第一歩を考えていきましょう。
不妊治療のステップとは?基本的な流れを理解しよう
不妊治療の3つの基本ステップ
不妊治療は一般的に「ステップアップ方式」で進められます。これは身体への負担が少ない治療から始めて必要に応じてより高度な治療へと移行していく方法です。
基本的な3つのステップは以下の通りです。
タイミング法 :排卵日を特定しタイミングをとりより自然な形での妊娠を目指す方法
人工授精(AIH):排卵日を特定しタイミングをとる代わりに精子を子宮内に直接注入する形で妊娠を目指す方法
体外受精(IVF)と顕微授精(ICSI):育った卵子を採卵で体外にとり体外で精子と受精させ数日間培養した胚を子宮に戻すことで妊娠を目指す方法
ただし治療はタイミングやAIHからスタートしなければならないというものではありません。例えば35歳以上の方やAMH値(卵巣予備能の指標)が低い方は早期に体外受精を検討することもあります。また男性不妊の程度によっては最初から体外受精が推奨される場合もあります。
重要なのは「ステップ」という言葉に縛られずご夫婦の状況に最も適した治療を選択することです。私たち専門医は検査結果や年齢やこれまでの妊娠歴や経緯や合併症などを総合的に判断しておふたりに最適の治療計画を提案します。
なぜステップアップが必要なのか
ステップアップを検討する主な理由は3つあります。
第一に現在の治療で一定期間妊娠しない場合、同じ方法を続けても成功率が低下することが分かっています。例えばタイミング法を6周期以上続けてもそれ以降の妊娠率はほとんど上がりません。
第二に年齢による影響です。特に女性の場合、35歳を過ぎると卵子の質が徐々に低下し染色体異常のリスクも増加します。
そのため年齢に応じて治療のスピードを調整する必要があり、35歳以上の方には早めのステップアップをお勧めすることが多いです。
第三に検査で新たな問題が見つかった場合です。例えば卵管造影検査で卵管閉塞が判明した場合はタイミング法や人工授精では妊娠が困難なため、卵管の手術などの選択肢を提示したうえで体外受精をおすすめすることがあります。
多くのご夫婦とお話しする中で、ステップアップをすすめられると自分は自然に近い形で妊娠できないと捉えて落ち込んでしまう方が多くいらっしゃいますが、ステップアップは「諦め」ではなく「妊娠という結果のためのより確実な方法への切り替え」と捉えていただければと思います。
ステップ1:タイミング法から始める不妊治療
タイミング法の具体的な進め方
タイミング法は最も自然に近い不妊治療です。まず月経開始から10-12日目頃に超音波検査で卵胞の大きさを測定します。卵胞が18-20mmに達すると24-36時間以内に排卵が起こることが予測されるため、この時期に夫婦生活を持つよう指導します。
実際の診療では超音波検査に加えて尿中LH(黄体化ホルモン)検査や血液検査でより正確な排卵予測を行うこともあります。また排卵誘発剤(クロミッドやレトロゾール)を使用することで卵胞発育を促したりhCG注射などを併用することで排卵をより確実にすることも可能です。ただし排卵誘発剤を併用する場合は複数個卵胞が発育してしまうと多胎妊娠の可能性が高くなるため、リスクを避けるために卵胞の数は慎重にモニタリングが必要となります。
最新の知見では排卵日の2日前から排卵日までの3日間が最も妊娠しやすい期間とされています。また毎日の夫婦生活よりも1-2日おきの方が精子の質が良好に保たれるという研究結果もあります。こうした科学的根拠に基づいて各ご夫婦に最適なタイミングをアドバイスしています。
タイミング法が適している方の特徴
タイミング法は、以下の条件を満たす方に特に適しています:
- 女性の年齢が35歳未満
- 月経周期が比較的規則的(25-35日)
- 卵管の通過性が保たれている
- 男性の精液所見が正常範囲内
- 不妊期間が半年未満
経験上、比較的若年で排卵障害を伴うPCOS(多嚢胞性卵巣症候群)の方は排卵誘発治療を併用し適切なタイミング法で妊娠される方が多くいらっしゃいます。
また月経が順調な方で毎月の通院が困難な方には自宅での排卵検査薬の使用と来院できる場合は超音波検査をすることを組み合わせた「セミセルフタイミング法」も提案し、なるべく通院が負担にならないような提案もしています。タイミング療法では現代のライフスタイルに合わせた柔軟な治療が治療継続の鍵となると考えています。
基礎体温と排卵検査薬の活用法
基礎体温は排卵の有無を確認する簡便な方法です。排卵後は黄体ホルモンの影響で体温が0.3-0.5度上昇し高温期が形成されます。ただし基礎体温だけでは排卵日を事前に予測することは困難なため、排卵検査薬との併用をお勧めしています。
市販の排卵検査薬は尿中のLHサージ(排卵前のホルモン急上昇)を検出します。陽性反応が出てから24-48時間以内に排卵が起こるため、陽性を確認したその日と翌日に夫婦生活を持つことが理想的です。最近ではアプリと併用することでご自身でもより正確な排卵日予測が可能になっています。
ステップ2:人工授精(AIH)への移行
人工授精の適応と成功率
人工授精はタイミング法と同様に排卵日を予測しタイミング指示の代わりに採精した精子を洗浄・濃縮して子宮内に直接注入する治療法です。主な適応は以下の通りです:
- タイミング法を3-6周期以上試みても妊娠しない場合
- 軽度の男性不妊(精子濃度1500万/ml以上、運動率30%以上)
- 子宮頸管粘液分泌不全
- 性交障害
- 原因不明不妊
人工授精の1周期あたりの妊娠率は5-10%程度です。これは自然妊娠率(20-25%)より低く見えますが、不妊症の方を対象としているため単純な比較はできません。累積妊娠率でみると、4-6回の施行で20-30%の方が妊娠に至ります。
最近の報告では、人工授精の成功率を高める要因として、以下が挙げられています。
- 処理後の運動精子数が1000万以上
- 女性の年齢が38歳未満
- 卵管の通過性が良好
- 適切な排卵誘発の併用
経験上は、特に軽度の男性不妊や比較的若年の排卵障害を伴う不妊の方で、良好な結果が得られることが多いです。
人工授精のスケジュールと注意点
人工授精の基本的な流れは以下の通りです。
| 月経3-5日目 | 排卵誘発剤の開始(必要に応じて) |
| 月経10-12日目 | 超音波検査で卵胞チェック |
| 卵胞が成熟したら | hCG注射で排卵を誘発 |
| hCG注射の翌日 | 人工授精実施 |
| 人工授精当日 | 採精した精液を洗浄・濃縮処理(約1-2時間)し、調整した精子を細いカテーテルで子宮内に注入 |
人工授精後の注意点として激しい運動は避けていただきますが、日常生活に制限はありません。シャワーや入浴も当日から可能です。また人工授精の前後でタイミングを持つことで妊娠率が向上するという報告もありますので、適宜タイミングをとっていただいて構いません。
排卵後の黄体補充療法(プロゲステロン製剤の使用)については個々の状況に応じて判断します。黄体機能不全が疑われる場合や35歳以上の方には積極的に行うことが多いです。
精子調整の重要性
人工授精における精子調整は単に精子を濃縮するだけでなく質の向上も目的としています。精液中には精子以外に白血球や細菌や死滅精子なども含まれており、これらが受精を妨げる可能性があります。
一般的には密度勾配遠心法やスイムアップ法を用いて運動性の高い精子を選別しています。最新の技術では精子のDNA断片化率を低下させる処理法も開発されており、これにより受精率や妊娠率の向上が期待されています。
また精子調整の際には精子の運動率や形態だけでなくミトコンドリア機能やアクロソーム反応能なども評価することがあります。これらの詳細な検査によりより効果的な治療戦略を立てることが可能になっています。
ステップ3:体外受精(IVF)と顕微授精(ICSI)
体外受精の種類と選択基準
体外受精は育った卵子を採卵で体外にとり体外で精子と受精させ数日間培養した胚を子宮に戻すことで妊娠を目指す方法で、受精方法には大きく分けて3つの方法があります:
- 通常体外受精(c-IVF):卵子と精子を培養液中で自然に受精させる方法
- 顕微授精(ICSI):1つの精子を卵子に直接注入する方法
- Split法:採卵した卵子を2群に分け、一部は通常体外受精、一部は顕微授精を行う方法
選択基準は以下の通りです。
- 精子濃度500万/ml以上、運動率30%以上 → 通常体外受精
- 重度の男性不妊、受精障害の既往 → 顕微授精
- 初回体外受精で精液所見が境界域 → Split法
現在日本では顕微授精の症例が増えています。これは男性不妊の増加とより確実な受精を求める傾向を反映しています。ただし顕微授精は通常体外受精と比べて費用が高く、胎児の異常リスクは自然妊娠と差がないと報告されていますが、一部の遺伝子異常や男性不妊の原因となる遺伝子が胎児に遺伝する可能性も指摘されており、適応は慎重に判断する必要があります。
採卵から移植までの詳細なプロセス
体外受精の治療プロセスは以下の段階に分かれます:
卵巣刺激(8-14日間)
FSH製剤やhMG製剤を使用して複数の卵胞を発育させます。刺激法には高刺激法(ロング法、ショート法、アンタゴニスト法、PPOS法)と中刺激法と低刺激法(クロミッド法、レトロゾール法)があり、AMH値や年齢やホルモン値などの反応性を考慮して選択します。
採卵(日帰り手術)
麻酔下で経膣超音波ガイド下で卵胞を穿刺し卵子を回収します。採卵数は個人差が大きく1-20個程度です。
受精・培養(5-6日間)
採卵当日に受精操作を行いその後5-6日間培養して胚盤胞まで育てます。培養中はタイムラプスインキュベーターで胚の発育を連続観察し最も良好な胚を選別します。
胚移植
新鮮胚移植または凍結融解胚移植を行います。最近では子宮内膜の着床能を最適化するため胚凍結後の融解胚移植が主流となっています。移植胚数は原則1個とし多胎妊娠を防止します。
黄体補充と妊娠判定
移植後は黄体ホルモン製剤で着床をサポートし、移植から10-14日後に血中hCG値測定で妊娠判定を行います。
最新の培養技術と成功率向上の工夫
近年の培養技術の進歩により体外受精の成功率は飛躍的に向上しています。主な技術革新には以下があります:
タイムラプスインキュベーター
胚の発育を24時間連続撮影し細胞分裂のタイミングや形態変化を詳細に観察できます。これにより外見上は同じグレードでもより着床能の高い胚を選別することが可能になりました。
培養液の最適化
胚の発育段階に応じて培養液の組成を変更するSequential mediaの使用により胚盤胞到達率が向上しています。また抗酸化物質の添加により培養環境のストレスを軽減しています。
AIによる胚評価
人工知能を用いた胚の自動評価システムが開発され胚培養士の主観的評価を補完しています。AIにより客観的な胚選別が可能になると期待されています。
これらの技術により35歳未満の方の胚盤胞移植あたりの妊娠率は50-60%で生産率は40-50%まで向上しています。
ステップアップのタイミングと判断基準

年齢別のステップアップ戦略
年齢は不妊治療において最も重要な因子の一つです。一般的に推奨される年齢別の治療戦略は以下の通りです:
30歳未満
- タイミング法:3-6周期
- 人工授精:3-6周期
- 一般不妊治療で結果が出なければ、適宜体外受精を検討
30-34歳
- タイミング法:3-4周期
- 人工授精:3-4周期
- 適宜体外受精への移行を推奨
35-37歳
- タイミング法:1-3周期
- 人工授精:1-3周期
- 積極的な体外受精の推奨
38-40歳
- タイミング法:1-3周期
- 人工授精: 1-2周期
- 早期の体外受精を強く推奨
41歳以上
- 体外受精を第一選択として提案
ただしこれはあくまで目安であり、卵巣予備能(AMH値)やホルモン値や基礎疾患の有無やパートナーの年齢や経済的事情なども考慮して個別に治療計画を立てます。特にAMH値が年齢の割に低い方は実年齢より高い年齢の戦略を提案することがあります。
検査結果に基づく個別化治療
現代の生殖医療では画一的な治療ではなく各種検査結果に基づいた個別化治療が重要です。主要な検査と治療方針への影響は以下の通りです:
AMH検査
卵巣に残っている卵子の数を推定する検査です。AMH値が1.0ng/ml未満の場合、卵巣予備能の低下が示唆され早期のステップアップを検討します。一方4.0ng/ml以上の場合はPCOSの可能性があり、排卵誘発を行う際は卵巣過剰刺激症候群(OHSS)に注意が必要です。
精液検査
WHO基準(2021年版)では精子濃度1600万/ml以上で運動率42%以上が正常とされています。これを下回る場合、程度に応じて人工授精や体外受精を選択します。またDNA断片化検査で高値の場合、抗酸化療法や生活指導とともに顕微授精などの受精方法についても適宜行います。
卵管造影検査
両側卵管閉塞の場合、卵管の手術についても説明したうえで体外受精を選択肢として推奨します。片側閉塞でも卵巣機能や年齢によっては早期の体外受精を推奨することがあります。
子宮鏡検査
子宮内膜ポリープや粘膜下筋腫が発見された場合、摘出手術を優先することがあります。慢性子宮内膜炎の診断がついた場合は抗生剤治療後に胚移植を行うこともあります。
AMH値と治療方針の関係
AMH値は治療方針決定において極めて重要な指標です。以下にAMH値別の具体的な治療戦略を示します:
AMH 0.1-1.0 ng/ml(低反応群)
- 採卵数が少ないことが予想されるため、早期の体外受精開始
- 低刺激法または自然周期採卵を選択
- 卵子の質改善のためにサプリメントの使用も提案
AMH 1.0-3.0 ng/ml(正常反応群)
- 標準的なステップアップを検討
- 年齢によっては、早期の体外受精を推奨
- 体外受精では中~高刺激法を推奨
AMH 3.0 ng/ml以上(高反応群)
- PCOSの可能性を考慮
- 排卵誘発剤への過剰反応に注意
- 体外受精ではOHSS予防のため、低刺激法か中刺激を検討し、全胚凍結を基本とする
AMH値は卵子の質を反映しないため、年齢と組み合わせて評価することが重要です。
不妊治療のオプションと併用療法
ERpeak検査やPGT-Aなどの先進医療
現在、不妊治療の成功率を高める様々な先進医療が利用可能です。
ERpeak(子宮内膜胚受容期検査)
反復着床不全の方を対象に子宮内膜の遺伝子発現を解析し最適な移植時期(着床の窓)を特定する検査です。約3割の方で着床の窓がずれており移植タイミングの調整により妊娠率が向上します。当院では良好胚を2回以上移植しても妊娠しない方に検査を推奨しています。
PGT-A(着床前胚染色体異数性検査)
胚盤胞から数個の細胞を採取し染色体の数的異常を調べる検査です。染色体正常胚の移植により流産率の低下と移植あたりの妊娠率向上が期待できます。35歳以上の方や反復流産の既往がある方に有用です。
子宮内膜スクラッチング
胚移植の前周期に子宮内膜を軽く傷つけることで着床率が向上するとされています。作用機序は完全には解明されていませんが、創傷治癒過程で産生される成長因子が着床に有利に働くと考えられています。
SEET法(子宮内膜刺激胚移植法)
胚培養液を凍結保存し移植の2-3日前に子宮内に注入することで子宮内膜の受容能を高める方法です。培養液中の胚由来因子が子宮内膜を刺激し着床環境を整えると考えられています。
男性不妊治療の重要性
不妊症の約50%に男性因子が関与しているにもかかわらず、男性不妊治療は女性よりも治療を後回しにしがちです。男性不妊治療には以下があります:
精索静脈瘤手術
精索静脈瘤は成人男性の15%に見られ精子形成に悪影響を及ぼすことがあります。顕微鏡下精索静脈瘤低位結紮術により精液所見の改善と自然妊娠率の向上が期待できます。手術適応は触知可能な静脈瘤があり精液所見が不良な場合です。
薬物療法
- クロミフェン:下垂体からのFSH/LH分泌を促進し、精子形成を改善
- hCG/FSH療法:低ゴナドトロピン性性腺機能低下症に有効
- 抗酸化療法:ビタミンE、C、コエンザイムQ10などで精子DNA損傷を軽減
精巣内精子採取術(TESE)
無精子症の方でも、精巣内には精子が存在することがあります。閉塞性無精子症では90%以上、非閉塞性でも30-50%で精子回収が可能です。採取した精子は凍結保存し、顕微授精に使用します。
生活指導
禁煙、節酒、適正体重の維持、サウナや長風呂の回避、締め付けない下着の着用など、生活習慣の改善も重要です。また、亜鉛やセレンなどの微量元素の補充も有効とされています。
統合的アプローチの効果
不妊治療では、西洋医学と補完代替医療を組み合わせた統合的アプローチも注目されています。
鍼灸治療
体外受精の前後に鍼治療を行うことで、妊娠率が向上するという報告があります。血流改善やストレス軽減が主な作用機序と考えられています。
ヨガ・瞑想
不妊治療中のストレスは、視床下部-下垂体-卵巣軸に影響し、ホルモンバランスを乱す可能性があります。ヨガや瞑想によるストレス管理は、治療成績の向上につながることが示されています。
栄養療法
- 葉酸:神経管閉鎖障害の予防だけでなく、卵子の質向上にも寄与
- ビタミンD:着床率や妊娠率と相関があり、不足者には補充を推奨
- オメガ3脂肪酸:抗炎症作用により、子宮内膜の環境を改善
- DHEA:卵巣予備能低下例で、卵巣反応性の改善が期待できる
運動療法
適度な運動は、インスリン抵抗性の改善、血流促進、ストレス軽減などの効果があります。BMI 25以上の方では、5-10%の体重減少により、排卵率や妊娠率が向上します。
心理的サポートと治療の継続
ステップアップ時の心理的負担への対処
不妊治療のステップアップは希望と不安が入り混じる複雑な心境を生み出します。「タイミング法で授からなかった」という事実に直面しより高度な治療への不安や経済的負担や仕事との両立など様々なストレスが重なります。
「ステップアップを勧められ、自分は自然に近い方法では妊娠できないのか」と暗い気持ちになっているみなさんにお伝えしたいのはステップアップは早く快適に目的地を目指すための抜け道や迂回路として捉えていただきたいということです。つまり渋滞でなかなか進まない道から一本道を変えてみると実は快適で目的地まで辿り着いたという経験と似ていると思います。さらに検査では何も問題なかったのになぜタイミング法でうまくいかないのかと考えてしまうことも多いようですが、体外受精にすすんでみると受精障害や胚の発育不良や着床不全などそれまで分からなかった原因が判明することも少なくありません。これはより的確な治療につながる重要な情報です。
また心理的負担を軽減するための具体的な方法として以下もお勧めです:
- 段階的な目標設定:「まず採卵まで」「良好胚ができたら移植」など、小さな目標を設定
- 情報の整理:治療内容や成功率について正確に理解し、過度な期待や不安を軽減
- サポートグループの活用:同じ経験をしている方との交流で孤立感を軽減
- 専門カウンセラーの利用:多くの不妊治療施設では心理カウンセラーが常駐
また、治療の一時的な休止も選択肢の一つです。心身ともに疲れを感じたら、1-3か月程度の休憩期間を設けることで、新たな気持ちで治療に臨めることがあります。
パートナーとのコミュニケーション
不妊治療は夫婦で取り組む共同作業ですが、温度差が生じることも珍しくありません。特に女性は身体的負担が大きく、男性はそれを十分に理解できない場合があります。
効果的なコミュニケーションのポイント:
- 定期的な話し合いの時間:治療方針や経済的な限界について、定期的に話し合う
- 感情の共有:「辛い」「不安」といった感情を素直に伝え合う
- 役割分担:通院の付き添い、薬の管理、情報収集など、できることを分担
- 二人の時間:治療以外の話題で過ごす時間も大切に
経験上、女性と男性がよく話合われて積極的に治療に参加しているご夫婦ほど治療で行き詰まった時に前向きに乗り越えることができ、最終的には卒業されていっていることが多いと思います。不妊治療では可能であれば精液検査の結果説明や体外受精の説明会などにはできるだけご夫婦で参加いただくといいと思います。
最後に不妊治療は確かに大変な道のりですが、現代医学の進歩により多くの方が赤ちゃんを授かることができるようになりました。一歩一歩ご自身のペースで進んでいけば、必ず希望の光が見えてくると信じています。私たち医療者はその道のりを全力でサポートさせていただきます。