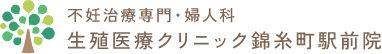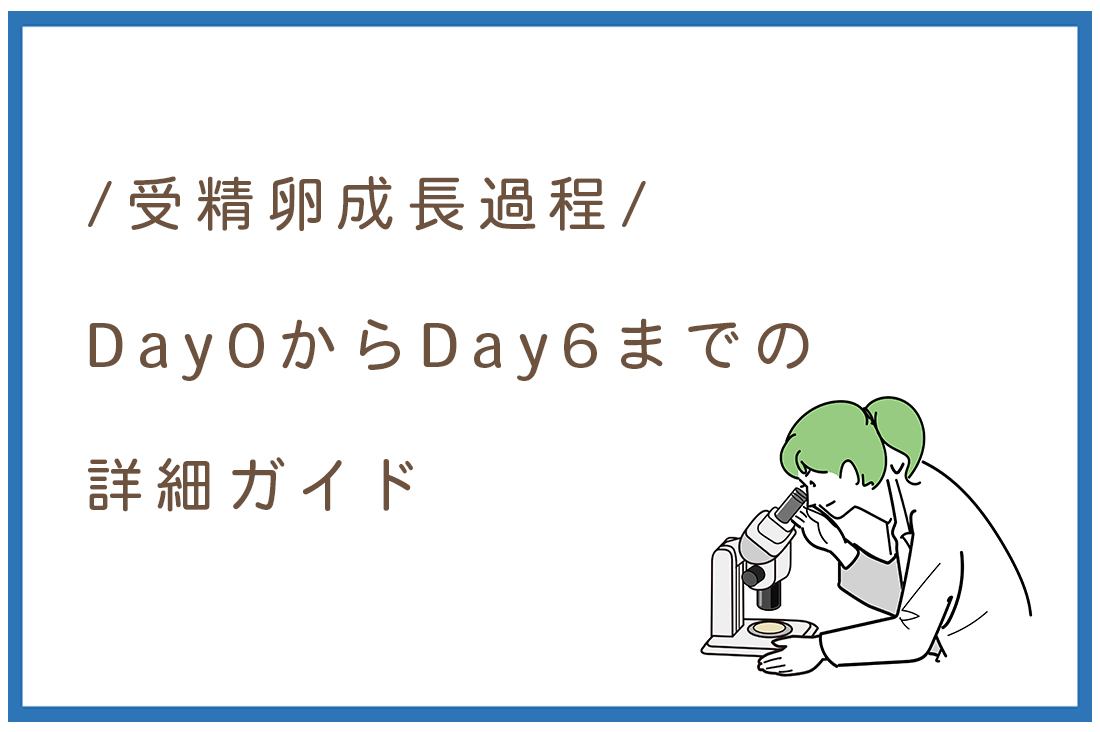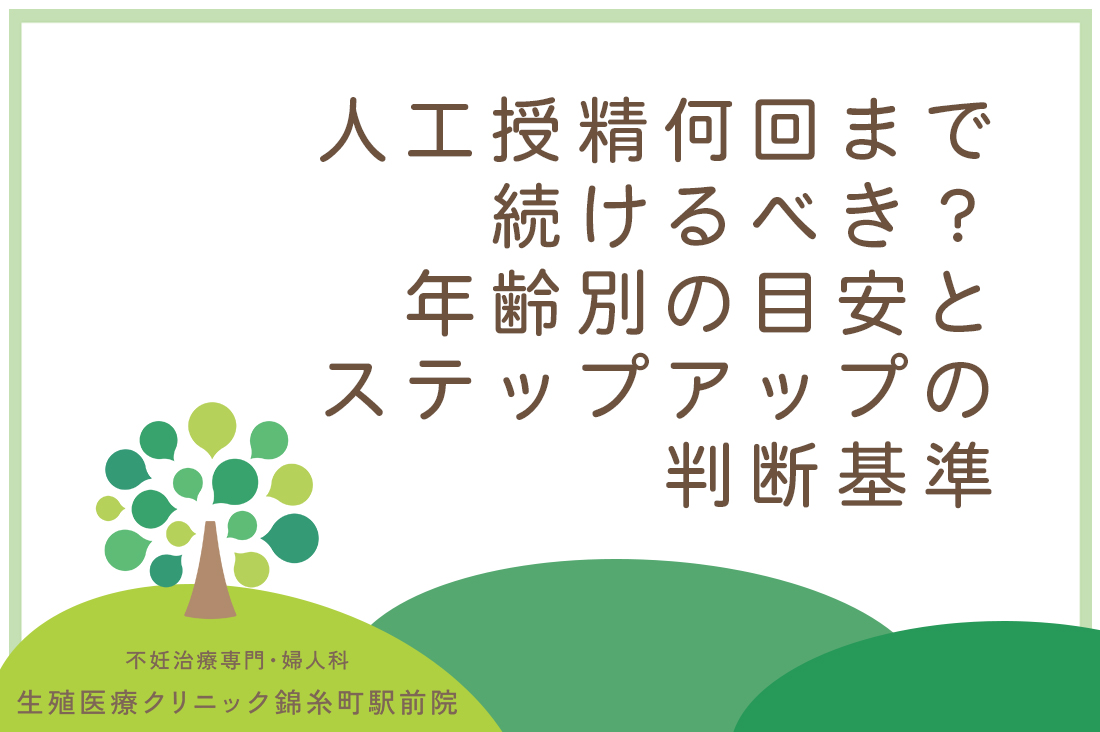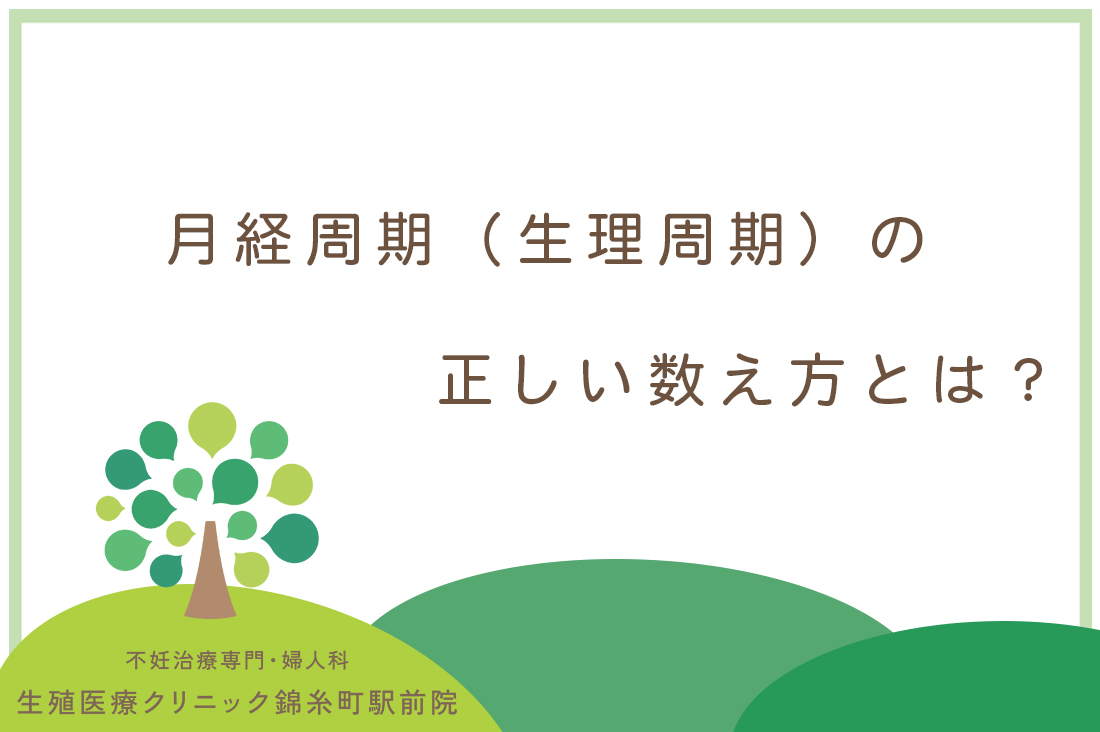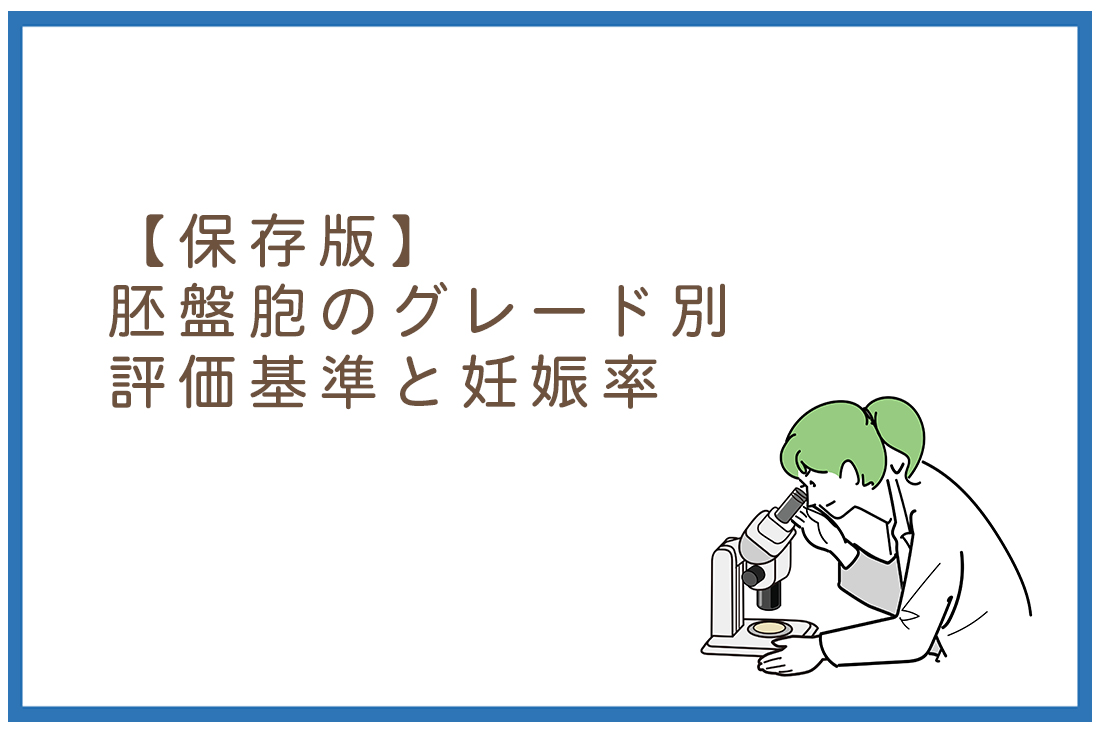目次
皆さんこんにちは。生殖医療クリニック錦糸町駅前院の胚培養士川口 優太郎です。
「今回採れた卵たちは無事に育ってくれるだろうか‥‥」
不妊治療、特に高度生殖医療を経験されている方ならきっと誰もが抱く不安ではないでしょうか?
通常の場合、採卵で採れた卵子は精子と媒精した後に最大で7日間培養されて胚盤胞と呼ばれるステージまで育てていきます。胚盤胞までしっかりと育つかどうかを待つこの一週間は期待と不安が入り混じり人によっては耐え難い期間かもしれません。
今回は我々がお預かりしている一週間の間に受精卵がどのように成長していくのか、そしてどのような変化が起こっているのかについてその過程や観察する際のポイントを分かりやすくお伝えできたらと思います。
このブログを読んで皆様が少しでも安心して治療に臨んでいただけたら幸いです。
受精卵の成長過程の基本|受精から子宮への着床まで
受精のメカニズムと最初の24時間
胚発生の過程は卵子と精子の受精から始まります。高度生殖医療においては採卵された卵子に精子を振りかけるように受精させる『体外受精(cIVF)』か精子を直接注入する『顕微授精(ICSI)』によって媒精していきます。
正常に受精が成立すると翌日に受精卵の細胞内に前核(PN;Pronucleus)が確認できるようになります。前核とは遺伝情報を含む核のことで、正常に受精した場合では卵子由来の遺伝情報を持つ核(雌性前核)と精子由来の遺伝情報を持つ核(雄性前核)の2つの前核が観察されます。
早いものでは媒精後6~8時間程度で前核が確認できるようになり20時間程度経過すると前核は消失します。我々胚培養士は採卵の翌日の媒精から16~20時間前後に観察を行い、この2つの前核の確認を以て正常に受精したか否かの判断をしています。
細胞分裂の始まり|2細胞期から8細胞期まで
受精から約20時間が経過すると前核が消失して細胞分裂(分割)が開始されます。教科書的に言えば1つの細胞が2つに→2つが4つに→4つが8つにといった具合に規則正しく分裂していくはずなのですが、胚培養士という立場から毎日のように受精卵を観察していると教科書通りに綺麗に分割が進んでいく受精卵ばかりではないな‥‥というのが実際のところです。
培養2日目の朝には4細胞期に、3日目には8細胞期に到達します。胚はこの段階で一度目の形態評価(グレード)が行われます。分割期胚はVeeck分類と呼ばれる評価方法に基づいてグレードが付けられ細胞割球の大きさの均等性やフラグメント(細胞の断片)の量などから判定されます。細胞割球が綺麗でフラグメントが少ない胚ほど良好な胚盤胞に発育する可能性が高い傾向にありますが、この時点ではまだ判断することは出来ません。少し成長がゆっくりだったりVeeck分類のグレードがやや低かったりする場合でも綺麗な胚盤胞に育つこともよくあります。
Compaction期、桑実期胚を経て、胚盤胞へ
培養4日目になると分割した細胞どうしが融合し始めます。この段階をCompaction期といいます。そして細胞が完全に融合して個々の細胞の境界が見えにくくなってくると桑の実のような見た目になってきます。この段階を桑実期胚(そうじつきはい)と呼びます。
その後に細胞の内部に空洞(胞胚腔)が形成され始め培養の5~6日目に胚盤胞(はいばんほう)へと成長します。
胚盤胞は子宮に着床した後に赤ちゃん本体を形成していく「内部細胞塊(ICM)」と胎盤を形成していく「栄養膜細胞(TE)」という2つの細胞群で構成されます。
胚培養士が受精卵を観察する際に着目するポイント
培養1日目:受精確認
採卵日の翌日である培養1日目に受精確認を行います。
正常に受精しているか否かでそこから長く培養を継続していくかどうかが決まるため培養における最初の重要な評価ポイントです。
先述した通り雌雄の2つの前核を確認することで正常な受精か否かを判断していますが、よくあるケースとして3つ以上の前核が認められる場合や前核が1つしか確認できない場合があります。いずれの場合も異常な受精の反応であるためこの時点で培養を中止します。
3つ以上の前核が認められる場合の原因としては1個の卵子に対して2個以上の精子が侵入する多精子受精が考えられます。
多精子受精の場合でも培養を継続すると胚盤胞まで成長することがありますが、赤ちゃんに育つ確率は0%でむしろ胞状奇胎などのリスクの高い異常妊娠につながる恐れがあるためこの段階で正しく見極めることが重要なポイントになります。
培養2~3日目:分割期胚の評価基準
分割期胚の観察では主に以下の3つのポイントを確認します。
分割速度
培養2日目におおよそ2~4細胞で3日目に8細胞程度に分割していないと成長速度としては遅いと判断されます。ただしこれより早すぎても遅すぎても発育に異常がある可能性があります。
割球の均等性
2細胞→4細胞→8細胞と細胞分裂を繰り返しながら発育していきますが、2細胞の段階でそれぞれの細胞の大きさが大小不同であったり4細胞の段階で大きい細胞や小さい細胞が混在しているとVeeck分類による評価は低くなります。
ただし2細胞→4細胞に分割する時に2つのそれぞれの細胞が全く同時に分割するわけではなくタイミングが少しズレることはよくあります。その場合は先に分割して2個になった細胞とまだ分割していない1個の細胞で3細胞期が観察されることがありこの場合は細胞の大きさに関する評価が少し変わってきます。
フラグメントの割合
分割が進んでいく段階でフラグメントと呼ばれる細胞断片が出てくることがあります。フラグメントについてはとにかく少ないほどよいです。少量であれば発育には大きな影響はありませんがフラグメントの量が多い場合にはVeeck分類による評価は低くなります。
培養5~6日目:胚盤胞の評価基準
胚盤胞の観察では国際的に使用されているGardner分類と呼ばれる評価方法に基づいて観察を行っていきます。
この分類では胚盤胞の大きさや形態・状態を表す1~6の数字と内部細胞塊の状態を表すA~Cのアルファベット、そして栄養膜細胞の状態を表すA~Cのアルファベットを組み合わせて表記します。
例えば胚盤胞4ABという評価では4=拡張期胚盤胞でA=内部細胞塊の評価(細胞が密で多い)、B=栄養膜細胞(細胞の数がやや少ない、フラグメントがやや認められる)といった具合です。
一般的な胚盤胞発生率は約40~60%程度ですが患者様の治療時の年齢やバックグラウンドによって大きく変動します。
受精卵の成長に影響する要因
培養環境の重要性
受精卵の成長には母体の卵管や子宮内に近い環境を再現することが不可欠で、一般的にはインキュベーター(培養器)と呼ばれる装置によって受精卵を培養・管理していきます。
インキュベーターは温度(;体温と同じ37.0℃に保つ)と酸素濃度(;5%の低酸素環境)と二酸化炭素濃度(;5~6%前後)という環境を維持するように作られており、これらの条件がズレてしまうと受精卵の発育に大きな影響を与えてしまいます。
そのため培養室では24時間体制で培養環境のモニタリングを行い停電時にも対応ができるバックアップシステムを完備しています。
年齢による影響
女性の治療年齢は受精卵の成長に最も大きな影響を与える要因の一つです。高齢になるほど染色体異常を持つ卵子の割合が増加して受精卵の成長が途中で止まる確率や胚盤胞まで育っても流産・死産の確率が高くなります。
染色体異常のある卵子の割合は年齢とともに増加します。アメリカ生殖医学会の学術誌であるFertility&Sterilityに報告されているデータでは、
| 20代~34歳 | 10~20%程度に染色体異常の卵子が認められる |
| 35~39歳 | 25~40%程度に染色体異常の卵子が認められる |
| 40~41歳 | 70%以上に染色体異常の卵子が認められる |
| 42~43歳 | 80%以上に染色体異常の卵子が認められる |
| 44歳以上 | 95%以上に染色体異常の卵子が認められる |
と、40代に入ると卵子の染色体異常の割合は急激に増加することが示されています。
ただしこれはあくまで統計的なデータであり、受精卵が育たなかった場合でも年齢だけが理由ではないことも多いです。治療歴や生活習慣などご自身のバックグラウンドを正しく理解して最適な治療方針を医師と相談することが大事です。
精子の質
受精卵は精子と卵子が融合した細胞であるため当然ながら卵子側だけでは無く精子側の影響も非常に大きく受けます。
一般的な精液検査では精液量と精子濃度(数)と精子運動率と形態評価(奇形率)によって精子の状態を測っていきますが、近年ではDFI(精子DNA断片化指数)やORP(酸化ストレス値)といった精子の”質”を評価する検査も導入されるようになってきました。
精子の数や運動性に問題が無くてもDFIが著しく悪い値というケースもかなり多く存在し、従来であれば「男性側には問題無い」と考えられていた症例でもDFI検査が導入されたことにより『実は男性側に不妊の要因があった』と分かることも増えてきました。
DFIやORPは生活習慣の影響を強く受けることが知られており生活習慣を見直すことによってある程度の改善が期待できます。
培養技術と胚発生率向上への取り組み
タイムラプス培養の導入
従来の培養方法は観察をする際に一度インキュベーターから取り出して顕微鏡まで持ってきて観察を行う必要がありました。先述した通り受精卵の成長には母体の卵管や子宮内に近い環境を再現することが不可欠であるためインキュベーターの外の環境つまり我々が生活している環境では受精卵にとっては強い負荷がかかっていることが指摘されていました。
そこで近年多くの施設で導入されるようになってきたのがタイムラプスインキュベーターです。タイムラプスインキュベーターはインキュベーターの中にカメラが内蔵されており受精卵を外に取り出すことなく連続的に観察できるようになりました。
これによって培養環境が一定に保たれるので受精卵に負荷をかけることなく培養を継続することが可能となりました。
AI技術を活用した胚評価
またタイムラプスインキュベーターのいくつかの機種には人工知能(AI)を用いた胚の評価システムが完備されています。
数千から数万の胚画像データを学習したAIが従来の観察方法では見ることができなかった胚の連続的な胚発生過程から人間の目では判別しづらい微細な特徴を捉えて妊娠の可能性を予測していきます。ただし現状ではAIはあくまで補助的なツールであるため最終的な判断は経験豊富な医師・胚培養士が行います。
培養液の進化
培養液の組成も年々改良が重ねられています。最新の培養液には受精卵の成長を促進する成長因子や酸化ストレスから保護する抗酸化物質などが含まれています。
また個別化医療の考え方から患者様の状況に応じて培養液をカスタマイズする試みも始まっています。例えば高齢の方の受精卵にはミトコンドリア機能をサポートする成分を追加するなどの工夫がされています。
これらの進歩により以前は胚盤胞まで到達しなかった受精卵も成長する可能性が高まってきています。技術の進歩とともに多くの方に希望をお届けできることを胚培養士として誇りに思っています。
受精卵の成長を待つ期間の過ごし方
日常生活で気をつけること
採卵後や培養期間中の過ごし方についてよくご質問をいただきます。基本的には普段通りの生活で問題ありません。むしろいつもとは違う特別なことをしようとするとかえって身体に対してはストレスを感じてしまうこともあるため心身に良くない影響を与えかねません。
推奨される過ごし方としては、
- 規則正しい生活リズムを保つ
- バランスの良い食事を心がける
- 適度な運動(激しい運動は避ける)
- 十分な睡眠をとる
- リラックスできる時間を作る
反対に、避けていただきたいことには、
- 過度な飲酒・喫煙
- 極端な食事制限
- 暴飲暴食
- 過度のストレス
- 睡眠時間の不足
などに気を付けていただけたらと思います。
パートナーとのコミュニケーションの重要性
治療を進めていく上で大切なのは「あの時○○していれば‥‥」という後悔をしないようにすることです。
採卵後から培養の結果が出るまでの期間に「もっと出来たことがあるのではないか?」「あの時○○していた方がよかったのではないか?」と考える方も少なくないようです。
例えば体調を普段から整えておくことや栄養に過不足無くバランスの良い食事を摂ることやBMIに基づいて体重をコントロールすることなどご自身で取り組めることはたくさんあります。
自分自身で出来ることには積極的に取り組み後々後悔することが無いように普段から身体的・精神的に準備を進めていただくのがよいかと思います。
そして最も重要なのは不妊治療はご夫婦で取り組む治療であるということです。特に採卵後の培養期間中はパートナーとの絆を深める良い機会でもあります。
これまでの治療経過や情報とお互いの気持ちを共有してお二人の目標が同じであるかどうか、そしてその目標に向かって協力し合うということが非常に大事になります。もしも「実は治療に前向きではない」ということであっても素直な気持ちをしっかりと伝え合うことが大切です。
また結果についての心の準備も一緒にしておくとよいでしょう。最良の結果を期待しつつも様々な可能性について事前に話し合っておくことで実際の結果を冷静に受け止められます。
私自身は臨床で日々多くの患者様とお話しする機会がありますが実は男性も同じように不安を感じていることが多いです。不妊治療は夫婦のどちらかだけが受ける治療ではなく夫婦が揃って初めて実施することができる治療だということを改めて知っていただきたいです。
よくある質問と胚培養士からのアドバイス

Q1: グレードの低い受精卵でも妊娠できますか?
A1: グレードの低い胚であっても、妊娠・出産されている患者様はたくさんいらっしゃいます。
グレードは“見た目”の評価であるため、染色体の正倍数性や着床の能力を完全に反映しているものではないためです。また、着床が成立するためには、胚以外の要因も数多くあるため、反対にどんなに胚のグレードが高くても、子宮環境やホルモンの値などの条件が悪ければ妊娠は難しくなります。
Q2: 受精卵が胚盤胞まで育たなかった場合、何か問題があるのでしょうか?
A2: 必ずしも、受精卵にだけ問題があると言い切ることはできません。例えば、体外での培養環境が合わなかった可能性もありますし、その周期はたまたま状態が良く無く、次周期の採卵で良好な胚盤胞が得られるケースもあります。また、胚盤胞の発育がどのステージで止まってしまったかによって、その原因が異なる可能性もあります。大事なのは、一度の結果で判断せずに、医師や胚培養士と相談して最適な方針を決めることです。
Q3: 培養中の受精卵の様子を見ることはできますか?
A3: クリニックによって対応は異なりますが、多くの施設では、受精卵の培養が一通り終わった段階で結果としてお写真をお見せすることが多いです。頻繁に観察することは、受精卵にストレスを与える可能性があるため、受精卵を守るためにもなるべく静かに見守ることが重要となります。
Q4: 受精卵の成長を促進するために、自分でできることはありますか?
A4: 身体を健康な状態にすることが、細胞の質を向上させることにつながります。体調を普段から整えておく。栄養に過不足無くバランスの良い食事を摂る。十分な睡眠を取るようにする。運動する習慣を付ける。BMIに基づいて体重をコントロールする。ストレスコントロールを行う。など、ご自身で取り組めることはたくさんあると思います。
ただし、このような生活習慣に気を付けたからといって過度な期待は禁物です。
最後に、胚培養士からのメッセージ
今回のコラムでは受精卵の成長過程について解説をしてきました。これを読んでいる皆さんも小学校や中学校の頃に”せいぶつ”でカエルやウニの受精卵の発生を勉強したかと思いますが、私自身もこの分野への興味は”せいぶつ”の受精卵の発生からでした。
1つの小さな細胞が細胞分裂を繰り返してヒトへと発生していく過程は『生命の成り立ち』を追っているようで、そこにはいち科学者としての強い興味とともに生命を創り出す責任感を抱きます。
技術は日々進歩していますが、ただし受精卵が胚盤胞に育つかどうかや無事に着床するかどうかの”最後の一押し”となるのはわれわれ胚培養士が一つ一つの胚をどれだけ丁寧に扱うことができたか‥‥だと思っています。少なくとも私のチームは常にそのような視点と胚の扱いに責任を持つよう指導をしています。
不妊治療・高度生殖医療の道のりは決して平坦ではないかもしれませんが実際にこれまでに多くのご夫婦がその夢を実現されています。今後も患者様の夢の実現のために”最後の一押し”ができるよう皆さまの治療の伴走者になれたらと考えています。