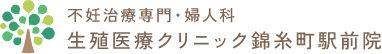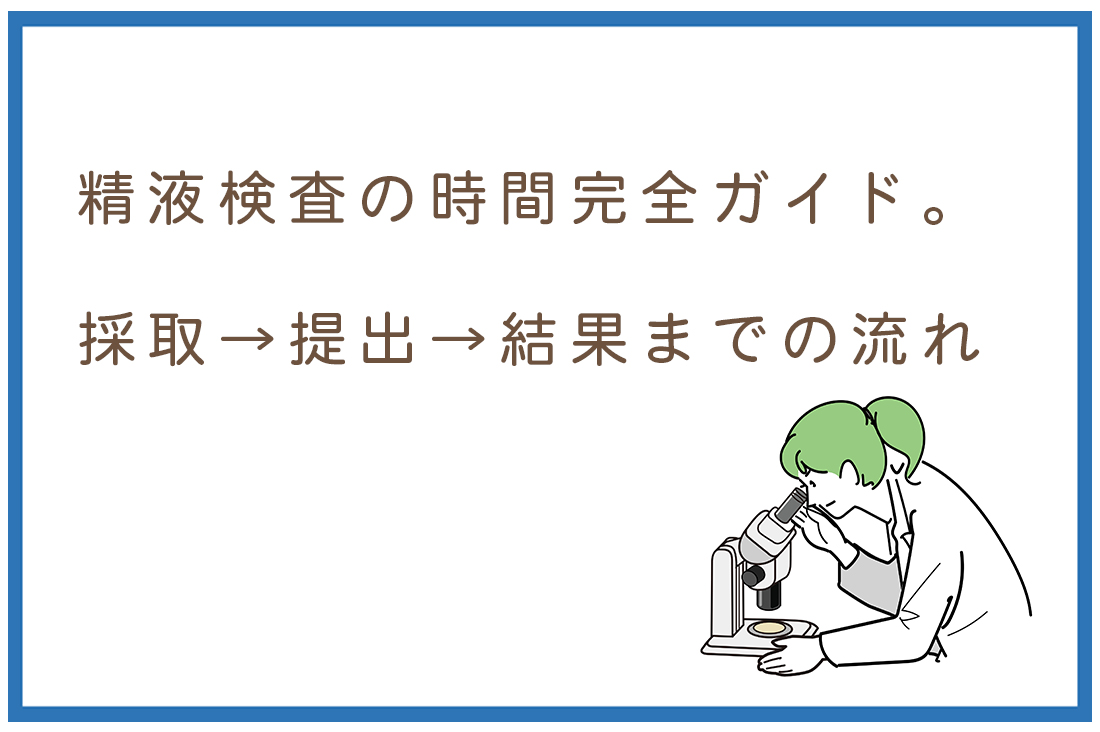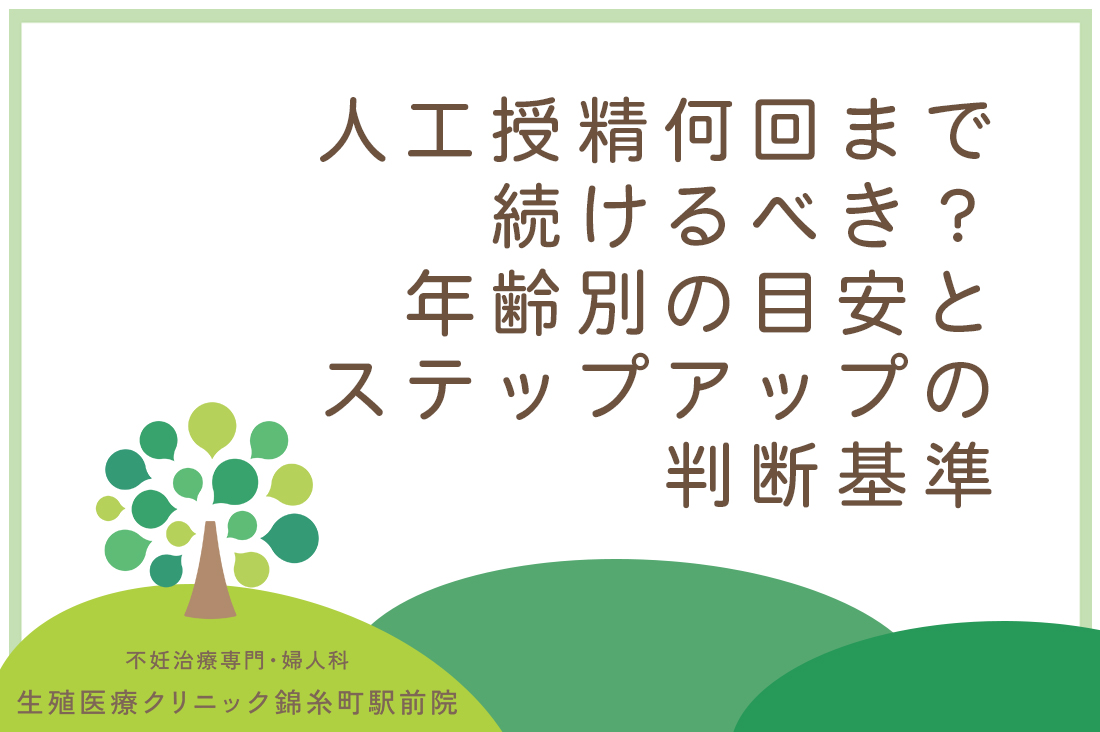目次
「精液検査を受けたいけれど、どのくらい時間がかかるんだろう」
「仕事が忙しくて時間が取れるか心配」
「採取してから病院に持っていくまで、どのくらいの時間なら大丈夫なの?」
不妊治療を進める上で精液検査は男性側にとっては欠かせない検査ですが、”時間”に関する情報が少なく戸惑う患者様も多いです。私は胚培養士として毎日のように精液検査を行っていますが、実は精液検査において”時間”は検査結果の正確性に大きく影響する重要な要素です。
今回のコラムでは精液検査に関わる”時間”について胚培養士の視点から詳しく解説します。
精液検査にかかる“時間” とは
初診での精液検査から結果説明までのタイムライン
検査のおおまかな流れとしては、
| 初診受付・問診(カウンセリング) | 15~30分 |
| 採精室での採取(採精) | 10~30分 |
| 検査実施 | 30~60分 |
| 診察・検査結果の説明(当日の場合) | 15~30分 |
| お支払い |
上記のように検査当日は初診受付から帰院するまでに最短で1時間弱、患者様の多い日は余裕を持って2時間程度を見込んでおくことをお勧めします。ただしこの流れは施設によって異なりますので、予約時に確認しておくとよいでしょう。
初診受付・問診(カウンセリング):15~30分
- 受付で検査の確認
- 検査同意書の記入
- 本人確認
初診時の問診・カウンセリングでは本人確認や保険証の確認などのほか不妊期間や治療歴や服薬歴や身長や体重や職業や他院での検査結果(※持っている場合)などに関してご夫婦揃って問診を行います。その後検査に進まれる場合には検査方法や注意事項などをお伝えします。
採精室での採取(採精):10~30分
- 採取容器へ名前・カルテNo.などの記入
- 採精:採精室(個室)で精液の採取
- 採精時刻の記入
多くの患者様が心配されているのが採精室の利用時間です。平均的には15~20分程度ですが慣れない環境での緊張などから時間が長くなる方もいらっしゃいます。時間制限などは設けていないという施設がほとんどですので、リラックスして望んでください。
ただし、常識的な時間を超過しても提出されないという場合にはお声をかけさせていただくこともあります。
検査実施:30~60分
- 精液検体の提出
- 液化
- 検査の実施
採精後検体を提出してから結果が出るまでの待ち時間はおおよそ30~60分となっており、やや長い待ち時間があります。実は検査の実施そのものにかかる時間はこれよりも短いのですが、正確に精液検査を行うためには精液の液化という工程が必要になります。射精後すぐの精液はゼリー状で粘性が高く、この状態では検査を行うことが出来ません。射精後の精子は一定の温度で15~30分程度静置することでさらさらの液体の状態に変化します。これは前立腺から分泌される酵素の働きによるもので、正常な精液の指標でもあります。
液化が極端に遅かったり不完全だったりする場合には前立腺の機能に問題がある可能性を示唆することがあります。
診察・検査結果の説明(当日の場合):15~30分
- 検査結果の説明
- 検査結果報告用紙のお渡し
- 結果に基づいた治療方針の策定
検査結果が出たら、再度診察にて結果説明を行います。検査結果に基づきタイミング法や人工授精などの一般不妊治療が適しているかあるいは体外受精や顕微授精などの高度生殖医療を行った方がよいのかといった治療方針の策定を行っていきます。
また検査によって無精子症や精子無力症といった重度の男性不妊の所見が見つかることもあります。そのようなケースでは男性不妊専門の泌尿器科クリニックなどを紹介することもあります。多くのクリニックがご夫婦で一緒に検査結果をお聞きになられることを推奨しています。
お支払い
診察代や検査費などをお支払いいただきます。当日の患者様の混雑具合などによっては算定までにお時間をいただくことがあります。
禁欲期間の適切な“時間”とは
なぜ禁欲期間は2~7日間がいいのか?
WHO(世界保健機関)のガイドラインでは精液検査を行う前に2~7日間の禁欲期間を置くことが推奨されています。「溜めておいた方がいいのでは?」あるいは「頻繁に出しておいた方がいいのでは?」と考える方も少なく無いのですが、この2~7日間という期間には医学的な根拠があります。
禁欲期間が2日未満の場合
禁欲期間が2日未満の場合では精液量や精子濃度が低下することがあります。特に精液量が低下してしまうと液化までに時間がかかったり検査のために扱うことができる検体の量が少なくなってしまったりと正確に検査結果を出すことが難しくなってしまいます。
禁欲期間が7日を超える場合
一方で禁欲期間が7日を超える場合では精巣上体に溜まった古い精子が増加するため、精子の運動率が顕著に低下していきます。またDFIなどのより詳細な検査でDNAにダメージを受けた精子の割合が増加することも知られています。
これらの理由から禁欲期間が短い場合でも長い場合でも、精子の受精能力が低下すると考えられています。
最適な禁欲期間の考え方とは?
胚培養士として毎日のように精液検査を扱っていますが、禁欲期間に影響を受けている精液検体を数多く目にします。また実際に精子を観察していると2~4日の禁欲期間を置いた場合で良好な結果が得られることが多い印象です。
ただし単純に『検査前に2~4日だけ禁欲期間を置けばいい』というわけではありません。
というのも例えば検査の前に射精したのが3日前であっても、その前に10日以上禁欲期間があるという場合には当然ながら検査結果に影響が出るということもよくあります。精巣では毎日毎日新しい精子が造られ続けているため、精子を造るだけではなく精子を排出する(射精する)ことも必要になります。
禁欲期間が長くなってしまうと古くなった精子が精巣内(精巣上体)にどんどん溜まっていき、禁欲期間が一定を超えてしまうと一度射精しただけではリセットされないこともあります。重要なのは2~7日間のペースで射精するサイクルを維持し常に造精と射精のバランスを保つよう意識することです。
採取から提出までの時間制限と注意点
なぜ精液検体の提出には時間制限があるのか?
精液検査では検体の提出に際してクリニック内で採精をして検体の提出を行う場合と自宅で採精してからクリニックに持ち込む場合があります。
持ち込みの場合、採精からおおよそ1時間以内に提出するように案内されますが、「なぜ1時間以内に持っていかなければならないのか?」という疑問を多くの方が抱かれます。これは簡潔に言えば時間の経過と環境・温度によって精液や精子の性状に変化が起こるためです。
1時間以上経過すると起こる精液の変化
1時間が経過をしてもすぐに精子が死んでしまい検査が出来なくなってしまう‥‥ということはありませんが、適切な環境下で検体を保管できないと正確な検査結果が得られなくなってしまうことがあります。
まず時間の経過とともに精子の運動率が低下していきます。精子は例えると卵子に辿り着くまで(卵管膨大部まで泳ぐことが出来る)の片道燃料を積んだロケットのような細胞であるため、時間が経過していくほど搭載している燃料の量が減っていき運動性がどんどん下がっていきます。運動性が低下し不動精子(動いていない精子)の数が増加すると、運動率や精子の生存率といった項目で検査結果が不正確になるリスクがあります。
加えて精液は尿道というあまり衛生的では無い経路を通って体外に射出されます。精液中には細菌が混ざっていることもあり、時間の経過とともに細菌の増殖リスクも高まります。
温度・環境の変化による影響
精子は温度変化に非常に敏感です。日本も温暖化の影響で猛暑日が続くこともありますが、精液は35℃以上の高温の環境に晒され続けると精子の運動性が失われていき、反対に低温の環境では精子の運動性が鈍くなっていき前進運動性が減少します。
採取後の精液検体は一般的な室温(25±5℃程度)の範囲内で保持することが理想的ですが、夏場/冬場などは測定している温度よりも高い/低い温度環境になることも多くあるため、特に注意が必要です。
夏場はなるべく早くクリニックに提出すること、冬場は容器をタオルで包むなどして外からの温度変化を受けにくくして提出することが推奨されます。電車の移動でよくあるのが外は雪が降って寒く電車内は空調が利いていて暑いといった具合に検体が極端な温度変化に晒されることで、このような影響を受けると精液データは露骨に悪くなってしまいます。
このような運搬時にかかったストレスによって正確な検査結果が得られず再検査になってしまう患者様も少なくありません。
検査結果が出るまでの“時間”

当日に聞ける検査項目と、後日聞く検査項目
精液検査には、当日に聞くことができる検査項目と、検査結果が得られるまでに時間を要し、後日にならないと聞くことが出来ない検査項目があります。
当日に結果がわかる項目
- 精液量:WHOの基準値では1.4ml以上が正常とされています。採取時の緊張やストレスで量が少なくなることもあります。
- 精子濃度:WHOの基準値では1mlあたり1,600万個以上が正常とされています。採取する日によって変動が大きくあります。
- 総精子数:WHOの基準値では3900万個以上が成長とされています。精液量に精子濃度を掛け合わせた値で、総精子数が多いほど妊娠の可能性が高くなると考えられています。
- 運動率:WHOの基準値では運動率は42%以上、そのうち前進運動精子が32%以上あれば正常とされています。採取後の時間経過や温度変化などで容易に低下してしまいます。
- 正常形態率・奇形率:WHOの基準値では正常形態率4%以上(奇形率96%未満)が正常な値とされています。精液中の精子には形態的に異常のある精子が非常に多く認められます。
上記のほかに精子の運動性(速度、移動経路など)も検査の当日にお伝えすることが可能です。
後日にならないと聞くことが出来ない項目
DFI(精子DNA断片化検査):
精子のDNAが損傷(断片化)している割合を示す指標です。精液検査で精子濃度や運動率に問題がなくても、DFIの値が高いことで、受精率、胚発生率の低下、着床率の低下、流産率の上昇などにつながる可能性が指摘されています。
ORP(精液中酸化還元電位検査)
精液の酸化ストレスレベルを測定する検査です。酸化ストレス値が高い状態は、精子に負荷がかかっている状態とされ、受精率や妊娠率の低下につながると考えられています。
上記のDFIやORPは精子の”質”や男性不妊の根本的な原因を評価する指標になると考えられており、一般的な精液検査とは別のより詳細な精液検査項目になります。
これらの検査を実施される場合では専門の検査機関に検体を送る必要があるため、結果が得られるまでに時間を要します。
クリニックによって異なりますが、おおよそ5日~1週間程度かかるのが一般的で夏季休暇や年末年始などではこれよりも長い時間を要することがあります。
DFIやORPを行う場合には後日一般的な検査項目と合わせて結果を聞くこともできます。
またお仕事などで忙しいという場合やパートナーと日程を合わせて一緒に聞きたいという場合にもまずは精液検体だけを提出して後日スケジュールを調整して結果を聞くということも可能です。
再検査を行った方がよいケースとは
先述した通り、精液検査の所見は採取してから検査までにかかる時間や温度・環境あるいは検査当日の体調やストレスなどにより大きく変動します。
1回だけの検査結果で治療方針や男性不妊かどうかを判断することは適切では無く、WHOにおいても『複数回の検査結果を以て判断することが望ましい』と規定されています。私自身がこれまでに実際に経験してきた患者様でも、初回の検査では基準値を下回っていた方が2回目や3回目と再検査を行ったところ正常な値を示したということもまったく珍しくありません。反面残念ながら検査をした時は正常な値であった方が人工授精や体外受精・顕微授精の当日に精子の状態が悪かったというケースもよくあります。
特に全体的な項目で基準値がギリギリの値という方では定期的に検査を受けることが望ましいでしょう。
再検査が推奨されるケース
- 検査結果が基準値を下回った場合
- 結果の数値に項目間でばらつきがあった場合
- 禁欲期間が不適切だった場合
- 体調不良時の検査だった場合
- 運搬時の環境や条件に問題があった場合
など、上記のような場合では再検査が推奨されます。また、
再検査はいつ頃行うべきか
体調不良や運搬時の人為的な理由など、一時的な要因や影響が疑われる場合には1~2週間程度の時間を置いて検査を行うことが推奨されます。
一方で、男性不妊など疾病が疑われる場合には、1ヶ月~3ヶ月程度の時間を置いて検査を行うことが推奨されます。精子は、精子の素となる細胞から体外に射出される精子と成るまでに74日間かかるとされています。そのため、より詳細な検査結果を得るためには上記の精子形成期間を考慮し、ある程度時間を置いてから検査を行う必要があります。
【Q&A】よくある質問に胚培養士がお答えします

Q1: 仕事の都合で日中に時間を取ることが難しい場合はどうしたらよいでしょうか?
A1: 朝一の時間帯や昼休みの時間帯などの空いている時間を利用して、精液検体をクリニックにお持ち込みいただき、検査結果は、後日スケジュールの合う日程にご来院いただき説明を受けることも可能です。
Q2: 平日は病院に行くことができません。どうすればいいですか?
A2: 多くの施設が土曜日も営業しているので、検査を受けることは可能です。また、自宅で採精してパートナー様に病院へ持ってきてもらうということも可能です。この場合、曜日に関係無く検査を受けることが出来ます。
Q3: 出張が多く、予定が立てにくいのですが検査は可能でしょうか?
A3: 予約変更が容易な施設や、当日予約が可能など、柔軟に対応してもらえる施設を選んでいただくのがよいでしょう。精液検体の提出のみであれば、自宅で採取しパートナー様に持ち込んでいただくことも可能であるため、ご来院は必要ありません。
Q4: 採取してから何時間以内に提出したらよいですか?
A4: 一般的には1時間以内が推奨されますが、どんなに遅くても2時間以内には提出いただけたらと思います。特に、朝の早い時間帯は気温が低いため、採取容器をタオルで包むなど慎重な温度管理が必要です。
Q5: 仕事帰りの19時以降に検査を受けられますか?
A5: 夜間診療を行っている施設もあります。ただし、遅い時間帯だと診療時間内に結果を出すことが難しい場合もあるため、まずは精液検体の提出を優先し、結果は後日聞くという選択も可能です。
Q6: 当日の滞在時間を最小限にしたいのですが?
A6: 問診票を自宅で記入してくる、保険証・紹介状を準備しておく、検査の流れを事前確認しておく、電話で混雑状況や所要時間を聞いておく、混雑しない時間帯を選ぶ、など対策を行うことで滞在時間を短くすることが可能になるかと思います。ただし、どんなに対策を行ってもイレギュラーなことが起こることも多々ありますので、時間に余裕を持ってご来院ください。
Q7: DFIやORPといった検査を、一般の精液検査と一緒にまとめて受けることはできますか?
A7: まとめて受けることは可能です。しかしながら、DFIやORPは結果が出るまでに時間がかかるため、検査当日にすべての検査結果を聞くことは不可能です。
Q8: 検査結果次第は、当日に再検査を受けることは可能ですか?
A8: 精子形成や精液検査の性質上、当日の再検査は医学的な価値が低いため実施はあまり意味がありません。検査時の状況により、おおよそ数週間から数カ月程度の時間を置いてから再検査されることが推奨されます。
まとめ
今回は精液検査に関する”時間”について解説を行ってきました。精液検査における”時間”は単なる数字ではなく精液の状態を正確に評価するためにあるいは適切な治療方針を立てるために重要な要素であることがお分かりいただけたのではないかと思います。
精液検体の採取から提出までの時間や液化の時間や適切な禁欲期間などを守ることで初めて精液を最良の状態で評価することが可能になります。
これまで胚培養士として数多くのご夫婦と接してきましたが、精液検査は『不妊治療の第一歩』であり結果次第で治療方針や治療の予後が変わっていくため、極めて大きな意味を持ちます。
“時間”を味方につけることでより良い結果へとつながる可能性も高くなります。
精液検査を受けることに不安を感じている方も多くいらっしゃるかもしれませんが、検査自体は痛みもなくプライバシーも守られています。また適切な時間の管理さえできれば、イメージしているよりも簡単に受けられる検査です。
まずはパートナーと一緒に不妊治療の『第一歩』を踏み出してみましょう。